喘息の咳と痰・痰の状態で疑われる疾患について解説!

喘息は気道の炎症によって引き起こされる呼吸器疾患です。
主な症状には咳や痰がありますが、これらの症状はほかの疾患でも見られるため、診断が難しい場合があります。
この記事では、喘息の咳と痰の特徴、痰の色や性状、疑われる疾患についてご説明いたします。
症状が当てはまる場合には、早めに呼吸器内科をはじめとする医療機関への受診を検討しましょう。
1. 喘息の咳と痰の特徴

喘息は気道の慢性的な炎症によって引き起こされる疾患です。
症状は患者さんそれぞれによって異なりますが、咳と痰は多くの方に共通して見られる症状です。
ここからは、喘息における咳と痰の特徴について詳しくみていきましょう。
1-1. 喘息における咳
喘息の咳には、いくつかの特徴的な性質があります。
まず、喘息の咳は痰を伴わない比較的乾いた空咳として現れる場合が多い点です(一方で、痰を伴う咳が出ることも見受けられます)。
この咳は、風邪やインフルエンザなどの感染症で見られるような、痰や鼻水が絡んだ咳とは異なります。
次に、咳の発症パターンには、さまざまな特徴があります。
多くの場合、最初は軽い咳から始まり、徐々に悪化していくことが一般的です。しかし、なかには突然激しい咳に襲われるケースもあります。
このように、咳の進行の仕方は患者さんによってそれぞれ異なり、個々の症状に合わせた対応が重要です。
喘息の場合、咳が出やすい時間帯や状況にも特徴があり、夜間から早朝にかけて咳が悪化する場合が多いです。
また、季節の変わり目や台風の接近時など、気圧や湿度の変化が大きい時期に症状が悪化しやすい傾向があります。
さらに、喘息の咳は特定の刺激によって誘発されることがあります。
たとえば、冷たい空気を吸い込んだ時や、たばこの煙やハウスダストにさらされた時、運動をした後などに咳が出やすくなることがあります。
喘息の咳のもうひとつの特徴は、その持続性です。
一般的な感染症による咳は2〜3週間程度で治まることが多いのですが、喘息の咳はそれ以上長く続くことがあります。
そのため、3週間以上咳が続く場合は、喘息やほかの慢性呼吸器疾患の可能性を考慮する必要があります。
最後に、喘息の咳は一過性であっても繰り返し起こる傾向があります。これは、咳が出ていない状態でも気道の過敏性が持続しているためです。
症状が一時的に改善しても、再び悪化することがあることも喘息の咳の特徴だといえます。
このように、喘息の咳にはさまざまな特徴がありますが、これらの症状は個人差が大きいため、必ずしもすべての方に当てはまるわけではありません。
ご自分の症状に不安がある場合は、早めに呼吸器内科をはじめとする専門医への受診を検討しましょう。
【参照文献】環境再生保全機構「もしかしてぜん息?」と思っている方へ
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/case/check.html
1-2. 喘息における痰
喘息の症状として咳と並んで注意すべきものが痰です。喘息における痰にも、いくつかの特徴的な性質があります。
まず、喘息の痰の量については、多くの場合、通常の風邪よりも増加する傾向があります。
これは、気道の炎症によって分泌物が増えるためです。
しかし、痰の量は個人差が大きく、また症状の程度によっても変化するため、必ずしも大量の痰が出るわけではありません。
痰の性状も喘息の際は特徴的です。多くの場合、透明または白色で比較的粘り気のある性質を持っています。
これは、気道の炎症によって分泌される粘液の性質を反映しています。ただし、感染症を併発している場合などは、痰の色や性状が変化することがあります。
痰の粘り気については、かなり強い場合があります。
とくに、アスペルギルスなどのカビが関連している喘息や重症の気管支喘息では、非常に粘り気の強い硬い痰が出ることがあります。このような硬い痰は気道を詰まらせる可能性があるため、注意が必要です。
痰が出やすいタイミングにも特徴があります。朝起きた直後や夜間に痰が増加すると感じている患者さんが多いです。
これは、体位の変化や気道の状態の日内変動と関連していると考えられています。
また、喘息の痰は、咳とともに症状が悪化する際に増加することが多いです。たとえば、アレルゲンにさらされたり、運動をしたりした後に痰の量が増えることがあります。
・痰の排出と気道クリアランス
喘息の患者さんでは、気道のクリアランス機能が低下していることがあります。
気道のクリアランス機能とは、肺や気道に入った異物(細菌・ウイルス・ホコリ・粘液など)を排除し、正常な呼吸を保つ仕組みのことです。
これは、喘息による慢性的な気道の炎症や構造的変化が原因となっています。
気道クリアランス機能には、粘液線毛エスカレータの働き、咳嗽(咳)の働き、肺胞マクロファージの働きという3つの重要な機能があります。
喘息の患者さんでは、これらの機能が障害されることがあり、痰の排出が困難になり、気道閉塞のリスクが高まる可能性があります。
適切な気道クリアランスを維持するためには、薬物療法による炎症のコントロールに加え、適切な排痰法を行うことが重要となります。
・痰と気道リモデリング
長期間にわたる喘息では、気道のリモデリング(構造的変化)が起こることがあります。リモデリングとは、慢性的な炎症反応の結果として生じる不可逆的な気道の構造変化を指します。
とくに粘液産生細胞の増加は、慢性的な痰の増加に直接関連します。
ただし、適切な治療によって症状がコントロールされると、痰の量や性状も改善することがあります。
以上のように、喘息の痰は、気道の状態を反映する重要な指標となります。痰の量や性状の変化は、喘息の症状の悪化や改善を示唆することがあるため、自己管理の上でも重要です。
ただし、喘息における痰にはこのような特徴がありますが、これらの症状は個人差が大きいため、必ずしもすべての方に当てはまるわけではありません。
【参照文献】 環境再生保全機構『ぜん息とは』
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/knowledge/index.html
2. 痰の色・性状で疑われる疾患
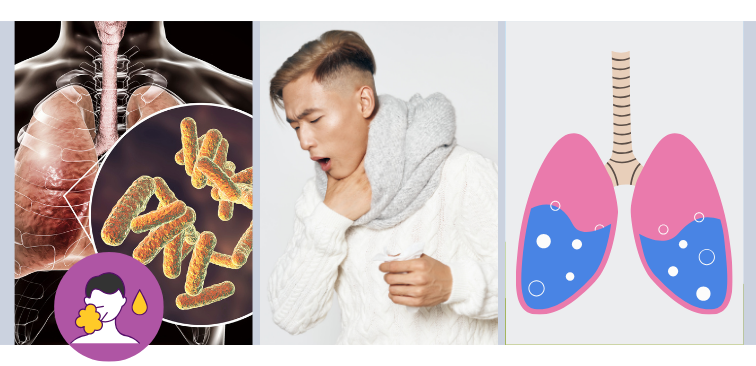
痰の色や性状は、さまざまな呼吸器疾患の診断や経過観察において重要な情報となります。
ここからは、痰の色や性状から疑われる可能性のある疾患についてご説明しましょう。
【透明または白色の痰】
透明や白色の痰は、一般的に正常な状態や軽いのどの刺激が原因で出ることが多いです。
しかし、量が増加したり、粘り気が強くなったりする場合は、以下のような疾患が疑われます。
・喘息
とくに初期段階や軽症の喘息では、透明または白色の痰が見られることがあります。
・アレルギー性鼻炎
鼻からのどに流れ込む分泌物が、透明または白色の痰として認識されることがあります。
・慢性閉塞性肺疾患(COPD)
初期段階では、透明または白色の痰が見られることがあります。
・ウイルス性上気道感染
初期段階では、透明または白色の痰が増加することがあります。
【薄い黄色の痰】
薄い黄色の痰は、軽い炎症や感染の可能性があります。考えられる病気として、以下のようなものがあります。
・軽度のウイルス感染
風邪やインフルエンザの初期段階で見られることがあります。
・慢性気管支炎
長期的に薄い黄色の痰が続く場合があります。
・気管支拡張症
慢性的に薄い黄色の痰が出ることがあります。
・喘息の悪化
通常は透明または白色の痰ですが、症状が悪化すると薄い黄色に変化することがあります。
【黄緑色の濃い痰】
黄緑色で濃い痰は、強い炎症や細菌感染の可能性が高いです。考えられる病気として、以下のようなものがあります。
・細菌性肺炎
黄緑色の濃い痰は、細菌性肺炎の症状のひとつです。
・気管支炎の悪化
慢性気管支炎が悪化すると、痰の色が濃くなることがあります。
・副鼻腔炎
後鼻漏として黄緑色の分泌物が喉に流れ込むことがあります。
・嚢胞性線維症
遺伝性疾患である嚢胞性線維症は、濃い黄緑色の痰が特徴的です。
・血痰(赤っぽい、茶色の痰)
血痰は、気道や肺からの出血を示す重要なサインです。考えられる病気として、以下のようなものがあります。
・激しい咳による咽頭粘膜の損傷
咳の衝撃で、喉の粘膜を傷め、そこから出血することがあります。
・気管支炎や肺炎の重症化
強い炎症により、少量の出血が起こることがあります。
・肺がん
持続的な血痰は、肺がんの可能性を示唆することがあります。
・結核
慢性的な血痰は、結核の症状のひとつです。
・気管支拡張症
気管支拡張症では、時に血痰が見られることがあります。
・肺塞栓症
急性の血痰は、肺塞栓症の可能性を示唆することがあります。
◆『血痰が出た!原因と呼吸器内科を受診する目安を解説します』>>
【ピンク色・オレンジ色の痰】
ピンク色・オレンジ色の色の痰は、以下のような疾患や状態のサインを示すことがあります。
・心臓性肺水腫
ピンク色の泡沫状の痰は、心臓の問題による肺水腫の可能性を示唆します。
・レジオネラ肺炎
オレンジ色の痰は、レジオネラ菌による肺炎の可能性を示唆します。
・慢性閉塞性肺疾患(COPD)の急性増悪
気道の炎症が進行し、気道内で軽い出血が起こると、ピンク色がかった痰が見られることがあります。
痰の変化に気がついた場合は、そのほかの症状も含めて総合的に評価し、必要に応じて専門医の診察を受けることが重要です。
さらに、痰の色や性状は喫煙、食べ物、飲み物、薬の影響でも変わることがあります。そのため、普段の生活習慣や飲んでいる薬も関係していないか考えることが大切です。
気になる症状がある場合は、自己判断は避け、早めに医療機関への受診を検討しましょう。
とくに、血痰や持続的な痰の変化がある場合は、速やかに専門医の診察を受けるようにしましょう。
3. 黄色い痰の理由
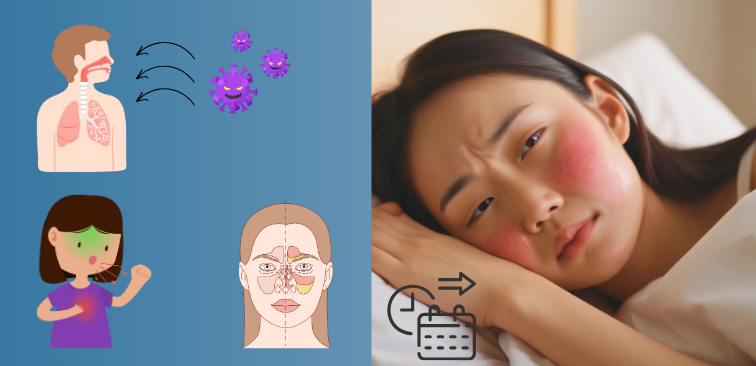
黄色い痰は、多くの患者さんが経験する症状のひとつです。
黄色の痰はさまざまな原因で引き起こされますが、主に炎症や感染に関連していることが多いと考えられます。
ここでは、黄色い痰が出る理由と、それによって疑われる疾患についてご説明いたします。
【黄色い痰の形成の仕組み】
黄色い痰は、からだが感染や炎症と戦う免疫反応の際に生じる現象です。この工程は以下のように進行します。
1. 免疫細胞の動員
体内に細菌やウイルスが侵入したり、炎症が起こったりすると、免疫システムが活性化します。
この時、好中球という白血球がはじめに集まってきます。好中球はからだの防御の最前線で働く重要な細胞です。
2. 特殊な酵素の存在
好中球のなかには、ペルオキシダーゼという特殊な酵素が大量に含まれています。
【ペルオキシダーゼ(POD)・・・過酸化水素(H2O2)の存在下で酸化反応を触媒する酵素。微生物や植物、動物に広く分布しており、生体内の活性酸素を消去する役割を担っている。】
3. 免疫細胞の破壊
好中球が病原体と戦う過程で、多くの好中球が破壊されます。これは正常な免疫反応の一部です。好中球が破壊されると、中に含まれていたペルオキシダーゼが放出されます。
4. 痰の着色
放出されたペルオキシダーゼが粘液(痰の主成分)と混ざることで、痰全体が黄色く着色されます。これが私たちが目にする黄色い痰の正体です。
【黄色い痰の意味】
黄色い痰が出ることは、からだが何らかの感染や炎症と戦っている証拠と言えます。
しかし、これは必ずしも重大な病気を意味するわけではありません。多くの場合、風邪や軽い気管支炎などでも黄色い痰が出ることがあります。
ただし、以下のような場合は医療機関での診察を検討しましょう。
・痰の量が急に増えた
・痰に血が混じっている
・高熱や息苦しさを伴う
・症状が長期間(2週間以上)続く
【黄色い痰が示唆する可能性のある疾患】
黄色い痰が見られる場合、以下のような疾患が疑われます。
・上気道感染症
風邪やインフルエンザなどのウイルス性上気道感染症の場合、初期には透明な痰が出ますが、数日経つと黄色い痰に変化することがあります。
・急性気管支炎
ウイルスや細菌による気管支の炎症で、咳とともに黄色い痰が出ることが特徴的です。
多くの場合、1〜3週間程度で自然に改善しますが、症状が長引く場合は医療機関の受診が必要です。
・細菌性肺炎
細菌による肺の感染症で、黄色や緑色の濃い痰が出ることがあります。発熱や呼吸困難を伴うことが多く、早期の治療が重要です。
・慢性閉塞性肺疾患(COPD)の急性増悪
COPDの患者さんが感染症にかかると、通常よりも痰の量が増え、色が黄色く変化することがあります。
・副鼻腔炎
副鼻腔の炎症により、黄色い鼻汁が喉に流れ込み、それが痰として認識されることがあります。
・気管支拡張症
気管支が異常に拡張する疾患で、慢性的に黄色い痰が出ることがあります。
・嚢胞性線維症
遺伝性疾患のひとつで、粘り気の強い黄色い痰が特徴的です。
・喘息の悪化
通常、喘息の痰は透明または白色ですが、症状が悪化したり感染症を併発したりすると、黄色く変化することがあります。
【黄色い痰への対処法】
黄色い痰が出る場合、十分な水分摂取により痰を薄くし排出しやすくすることが大切です。
また、加湿をして気道の乾燥を防ぐことで痰の排出を促せます。
喫煙は気道を刺激し痰の産生を増加させるため、禁煙が重要です。
体位ドレナージを活用して重力を利用しながら痰を排出しやすくする方法もあります。
温かい飲み物を摂ることで気道を温め、痰の排出を促進することもいいでしょう。
痰を伴う咳は自然な排出反応であるため、むやみに抑えず適切に出すことが重要です。
もし黄色い痰が長期間続く場合や、発熱・呼吸困難などの症状を伴う場合は、早めに医療機関への受診を検討しましょう。
【注意点】
黄色い痰が出ているからといって、必ずしも抗生物質が必要というわけではありません。多くのウイルス性感染症では、抗生物質は効果がなく、自然に回復することがあります。
また、痰の色だけでなく、量や粘り気、ほかの症状(発熱、呼吸困難、胸痛など)も重要な情報です。これらの症状を総合的に評価し、適切な診断と治療を行うことが重要です。
ただし、黄色い痰が2週間以上続く場合や、症状が悪化する場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。
とくに、高齢者の方や基礎疾患をお持ちの方は、症状が重症化しやすいため、早めの受診しましょう。
【参照文献】環境再生保全機構 【知識編】痰の観察
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/copd/sputum/02.html
【参考情報】ClevelandClinic 『Coughing Up Phlegm』
https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/24636-coughing-up-phlegm
4. おわりに
咳や痰は、からだが何らかの異常に対して反応している重要なサインです。
とくに喘息の患者さんにとっては、これらの症状の変化に注意を払うことが、自己管理の上で非常に重要です。
長引く咳や痰の症状がある場合には、早めに呼吸器内科を受診しましょう。
専門医による適切な診断と治療により、症状の改善や疾患の進行予防が期待できます。




