深呼吸で咳がでたとき考えられる病気とは
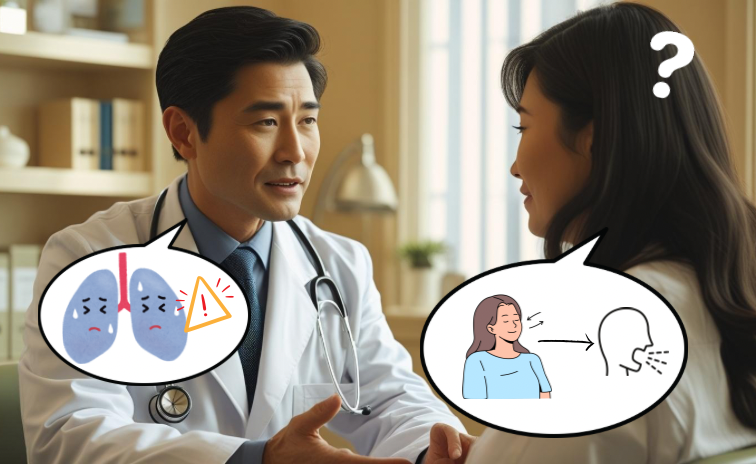
深呼吸は、私たちの心とからだの健康を支える大切な習慣です。
一方で、深呼吸をしたときに咳が出る場合、単なる一時的な不調ではなく、呼吸器の病気が原因であることもあります。
この記事では、深呼吸の健康効果や、咳が出る原因となる病気、対処法や日常の予防策についてご説明いたします。
1.深呼吸には様々な効果がある

深呼吸は、効果的で意識的に行える最も簡単な健康法のひとつです。
忙しい毎日のなかでは、つい浅い呼吸になりがちですが、深呼吸を意識的に取り入れることで、心身に多くの良い変化が現れます。
まず、深呼吸は体内に新鮮な酸素をたっぷり取り込むことができます。それにより血液中の酸素濃度が高まり、全身の細胞に十分な酸素が届けられます。
そのため、脳や筋肉、内臓などの働きが活発になり、疲労回復の促進が可能です。
たとえば、仕事や家事で疲れたとき、深呼吸を数回行うだけで頭がすっきりした経験がある方も多いのではないでしょうか。
また、深呼吸にはリラックス効果があります。
私たちのからだには「自律神経」と呼ばれる神経系があり、活動時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に優位になる「副交感神経」がバランスを保っています。
深呼吸は副交感神経を優位にし、自律神経のバランスを整える働きがあります。
そのため、緊張やストレスを感じたときに深呼吸をすると、心拍数や血圧が安定し、自然と心が落ち着いてくるでしょう。
さらに、深呼吸は睡眠の質を高める効果も期待できます。
寝る前に深呼吸を繰り返すことで、からだがリラックスモードに切り替わり、入眠しやすくなります。
実際に、不眠に悩む方に深呼吸を取り入れていただくと「夜中に目が覚めにくくなった」「朝までぐっすり眠れるようになった」という声をよく耳にします。
そして、深呼吸は血流を良くする効果もあります。
ゆっくりと大きく息を吸い込むことで胸郭(きょうかく:胸の骨格)が広がり、心臓や肺への血流が増えるのです。その結果、手足の冷えやむくみの改善にも役立ちます。
また、深呼吸によって体内の老廃物や二酸化炭素が効率よく排出されるため、デトックス効果も期待できます。
このように、深呼吸はリラックス効果、睡眠の質の向上、疲労回復、自律神経のバランス調整、血流改善、デトックスなど、多くの健康効果をもたらします。
特別な道具も場所も必要なく、どなたでも今すぐ始められる健康法です。忙しい毎日のなかでも、1日に数回深呼吸を意識してみてください。
きっと心もからだも軽くなるのを実感できるでしょう。
2.深呼吸で咳がでる?その原因とは

深呼吸をしたときに咳が出る場合、からだが何らかの異常を感じているサインかもしれません。
一時的な咳であれば心配いらないことが多いですが、繰り返し咳が出る、長期間続く、ほかの症状(息切れ、痰、発熱など)を伴う場合は、呼吸器の病気が隠れていることがあります。
ここでは、呼吸器内科でよく見られる主な原因疾患について、症状や原因についてご説明します。
2-1.COPD(慢性閉塞性肺疾患)
COPDは、「慢性閉塞性肺疾患」と呼ばれる病気で、主に長年の喫煙や大気汚染が原因で、気管支や肺が慢性的に炎症を起こし、呼吸がしづらくなる病気です。
とくに40歳以上の中高年の方に多く見られ、患者さんの数は年々増加しています。
COPDの主な症状は、「咳」「痰」「息切れ」です。
初期のうちは、朝方に痰がからむ咳が出る程度ですが、進行すると階段や坂道で息切れが目立つようになります。進行性の病気のため、放置すると呼吸機能がどんどん低下してしまいます。
また、風邪をひいた後に咳だけがなかなか治らない、というケースも多いです。
深呼吸をすると、気道が狭くなっている部分に空気が強く流れるため、咳が誘発されやすくなります。
重症化すると、日常生活に大きな支障をきたし、在宅酸素療法が必要になることもあります。
COPDの最大のリスク要因は「喫煙」です。
タバコの煙は気道や肺に強い刺激を与え、炎症や組織の破壊を引き起こします。現在タバコを吸っている方は、できるだけ早く禁煙することが非常に重要です。
禁煙によって病気の進行を遅らせることができ、咳や痰の症状も改善しやすくなります。
ご自身やご家族に喫煙者がいる場合は、ぜひ一度、早めに禁煙を検討しましょう。
また、COPDは早期発見・早期治療がとても大切です。
「年齢のせいかな」「ただの風邪かな」と思っても、咳や息切れが続く場合は、呼吸器内科を受診し、肺機能検査(スパイロメトリー)を受けてみましょう。
早期に治療を始めることで、進行を抑え、快適な生活を続けることができます。
【参考情報】Mayo Clinic『COPD』
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/copd/symptoms-causes/syc-20353679
2-2.慢性咳嗽(まんせいがいそう)
慢性咳嗽とは、8週間以上続く咳のことを指します。
風邪が治った後も咳だけが長引く場合や、特定の季節や環境で悪化する場合など、患者さんによって症状や原因はさまざまです。
慢性咳嗽の主な原因には、以下のようなものがあります。
・喘息:気道が過敏になり、少しの刺激で咳が出やすくなる
・アトピー咳嗽:アレルギー体質の方に多く、痰を伴わない乾いた咳が続く
・逆流性食道炎:胃酸が食道に逆流し、喉や気道を刺激して咳が出る
・後鼻漏(こうびろう):副鼻腔炎などで鼻水が喉に流れ込み、咳が出る
【後鼻漏(こうびろう)・・・慢性副鼻腔炎や好酸球性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎患者に見られる咽頭腔への膿汁流下のこと。】
上記のような疾患の方は、深呼吸によって気道が刺激されることで咳が出やすくなることがあります。
とくに、空気の乾燥や冷たい空気、タバコの煙、花粉などの刺激で症状が悪化しやすいです。
慢性咳嗽は、咳そのものが生活の質を大きく下げる原因となります。
「夜中に咳が止まらず眠れない」「人前で咳が出てしまい困る」「仕事や家事に集中できない」など、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。
原因によって治療法は異なるので、自己判断で市販薬を使い続けるのではなく、専門医の診断を受けましょう。
2-3.喉頭アレルギー
喉頭アレルギーとは、ダニやハウスダスト、花粉、ペットの毛などのアレルゲンが喉頭(喉の奥)に作用して、咳や喉の不快感、違和感を引き起こす病気です。
アレルギー体質の方や、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎をお持ちの方に多く見られます。
症状は、喉の奥がかゆくなったり、イガイガしたりすることが特徴です。
とくに季節の変わり目や花粉の多い時期、または部屋の掃除をした後などに症状が強くなる方が多いとされています。
咽頭アレルギーの方は深呼吸で空気が喉を通る際にアレルギー反応が強くなり、咳が出やすくなります。風邪や感染症とは違い、発熱や強い喉の痛みはあまり見られません。
一方で、咳が長引いたり、喉の違和感が続くことで日常生活に支障をきたすことがあります。
治療には、抗ヒスタミン薬や点鼻薬がよく使われます。
また、アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎を合併している場合は、その治療も同時に行うことが大切です。
アレルゲンをできるだけ避ける生活環境の工夫(こまめな掃除、空気清浄機の使用、マスクの着用など)も有効です。
喉頭アレルギーは、患者さんご自身が「風邪が治らない」「いつも喉が変」と感じて受診されることが多いですが、適切な治療と生活改善で症状が改善するケースがほとんどです。
◆『咳が止まらないのはなぜ?アレルギーが原因かもしれません』>>
2-4.喘息
喘息は、気道が慢性的に炎症を起こし、過敏になっている状態です。
気道が狭くなり、息苦しさや咳、喘鳴(ぜんめい:ヒューヒュー・ゼーゼーと音がする呼吸)が主な症状です。
お子さまから大人の方まで幅広い年代で発症しますが、近年は大人になってから発症する「成人発症喘息」も増えています。
喘息の咳は、夜間や早朝に悪化することが多く、季節や環境の変化、運動、冷たい空気、タバコの煙、ストレスなどで症状が強くなることもあります。
喘息の方が深呼吸をしたときに咳が出るのは、気道が刺激されやすくなっているためです。
喘息の咳は、痰を伴わない乾いた咳が多いです。
咳が長引く場合や、息苦しさ、胸の圧迫感、呼吸時の音(喘鳴)がある場合は、喘息を疑う必要があります。
喘息は、放置すると発作が重症化することもあるため、早期の診断と治療が重要です。
市販薬で一時的に症状を抑えることはできても、喘息は根本的に治すことが難しいため、専門の呼吸器内科医による診断と治療が不可欠です。
吸入ステロイド薬や気管支拡張薬など、患者さんの症状や重症度に合わせた治療が必要です。
自己判断で市販薬を使い続けるのではなく、必ず専門医の診察を検討しましょう。
また、喘息は適切な治療と自己管理によって、発作を予防し、日常生活を快適に送ることが可能です。
「咳が続くだけだから」「昔から喘息気味だから」と軽く考えず、症状があれば早めに受診をすることができます。
【参照文献】環境再生保全機構『はじめてぜん息と診断された方へ|成人ぜん息(ぜんそく、喘息)』
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/case/first.html
2-5.マイコプラズマ肺炎
マイコプラズマ肺炎とは、Mycoplasma pneumoniae(マイコプラズマ・ニューモニエ)という非常に小さく特殊な細菌によって引き起こされる肺の感染症です。
この細菌は細胞壁を持たないため、一般的な細菌とは異なり、特定の抗生物質が効きにくいという特徴があります。
マイコプラズマ肺炎は、特にお子さまや若い年齢の方に多く見られ、毎年報告される患者の約80%は14歳以下ですが、大人の方や高齢者の方でも発症することがあります。
一年を通じて発生しますが、特に秋から冬にかけて流行が目立ちます。
感染経路は主に飛沫感染(咳やくしゃみによる唾液や分泌物の吸入)や接触感染(分泌物が付着した物に触れた手で口や鼻、目に触れる)によってです。
学校や職場、保育施設など集団生活の場では、密接な接触が多いため感染が拡大しやすく、家族内感染も高い確率で起こります。潜伏期間は2〜3週間と比較的長く、知らないうちに感染が広がることも少なくありません。
主な症状は、発熱(38〜39度程度)、乾いた咳、喉の痛み、全身のだるさ(倦怠感)、頭痛などです。
咳は最初は軽く、痰を伴わない乾いた咳が特徴ですが、徐々に強くなり、特に夜間や早朝、深呼吸時や会話中に咳き込むことが増えてきます。
咳は熱が下がった後も3~4週間、時にはそれ以上続くことがあり、「頑固な咳」として知られています。
また、全身の倦怠感や頭痛、喉の痛みのほか、鼻炎症状、胸の痛み、まれに耳の痛み、吐き気、下痢、皮疹、喘鳴(ゼイゼイ・ヒューヒューという呼吸音)などの症状が現れることもあります。
一部の患者さんでは、中耳炎、心筋炎、無菌性髄膜炎、脳炎、肝炎、溶血性貧血などの重い合併症を伴う場合もあります。
マイコプラズマ肺炎は「歩く肺炎(walking pneumonia)」とも呼ばれ、発熱や咳が続いていても比較的元気そうに見えることが多く、日常生活を続けながら感染を広げてしまうことがあるのが特徴です。
診断には症状の経過や身体所見に加え、画像検査(X線やCT)、血液検査(抗体検出)、遺伝子検査(PCR)、迅速診断キットなどが用いられます。当院では、遺伝子検査と迅速診断キットには対応しておりません。
特に咳が長引く場合や、発熱が続く場合は医療機関を受診し、これらの検査を受けることが重要です。
治療には、マクロライド系抗生物質(クラリスロマイシンやアジスロマイシンなど)が第一選択として使用されます。
マイコプラズマは細胞壁を持たないため、ペニシリン系など一般的な抗生物質は効果がありません。
また、自己判断で市販の咳止め薬を長期間使用し続けると、症状が悪化したり、重症化することもあるため注意が必要です。
多くの場合は軽症で済みますが、重症化した場合や合併症が疑われる場合には、入院治療が必要になることもあります。
マイコプラズマ肺炎は家族や周囲の人にも感染する可能性が高いため、以下の感染予防策が大切です。
・咳エチケット(咳やくしゃみをする際は口や鼻を覆う)
・マスクの着用
・石けんと流水による手洗いの徹底
・タオルや食器の共用を避ける
・感染者との濃厚接触を避ける
有効なワクチンは現在ありませんが、これらの日常的な予防策を徹底することで感染拡大を防ぐことができます。
お子さまや若い年齢の方は比較的軽症で済むことが多いですが、高齢者や基礎疾患(喘息や心臓病など)のある方、免疫力が低下している人は重症化しやすく、合併症のリスクも高まります。
特に高齢者の方では典型的な症状が現れにくい場合があり、注意が必要です。
2-6.肺がん
肺がんは、肺の細胞が異常に増殖する悪性腫瘍です。
日本ではがんによる死亡原因の上位を占めており、年々患者さんが増加しています。
喫煙歴のある方や、家族に肺がんの方がいる場合は特に注意が必要です。
肺がんは初期には自覚症状がほとんどないことが多いですが、進行すると咳や血痰、息切れ、胸の痛み、体重減少などの症状が現れます。
深呼吸で咳が出る場合は、肺がんが気道を刺激している可能性も否定できません。また、がんが気管支や肺の周囲に広がると、咳が慢性的に続くことがあります。
肺がんの診断には、胸部X線検査やCT検査、喀痰細胞診、気管支鏡検査などが必要です。
早期発見が重要となるため、普段から定期的に健康診断や人間ドックを受け、異常があれば速やかに専門医に相談することが大切です。
肺がんの治療は、手術、抗がん剤治療、放射線治療、免疫療法など、がんの種類や進行度によって異なります。
早期発見・早期治療によって、治療成績が大きく向上するので、長引く咳や血痰などの症状がある場合は、決して放置せず、必ず受診してください。
3.おわりに
深呼吸は心身の健康維持に役立つ大切な習慣です。
深呼吸をした際に咳が出る場合、呼吸器の病気が原因である場合もあります。咳はからだからの重要なサインです。
咳が長引く、息切れや痰、発熱、胸痛、血痰などほかの症状が伴う場合は、早めに呼吸器内科への受診を検討しましょう。
咳の原因はひとつでなく、複数の要因が重なることもあります。自己判断での治療は危険な場合も考えられます。
呼吸器内科では症状や生活背景に応じて、必要な検査(胸部X線検査、CT、肺機能検査など)を行い、最適な治療法をすることが可能です。
咳予防のポイントとしては、室内の空気環境を整えること、マスク着用、禁煙、バランスの良い生活習慣、ストレス管理、定期的な健康診断が挙げられます。
咳は「たかが咳」と軽視せず、気になる症状があれば早めに受診しましょう。




