クラミジア・ニューモニエ肺炎とはどんな病気?

クラミジア・ニューモニエ肺炎は、クラミジア・ニューモニエという細菌によって起こる肺炎の一種です。
一般的な細菌性肺炎より症状が軽めでゆっくり進行しますが、咳が長引くことが特徴です。
感染力は高くありませんが、学校や職場などで集団発生することもあり、早めの対応と治療が大切です。
1. クラミジア・ニューモニエ肺炎の特徴
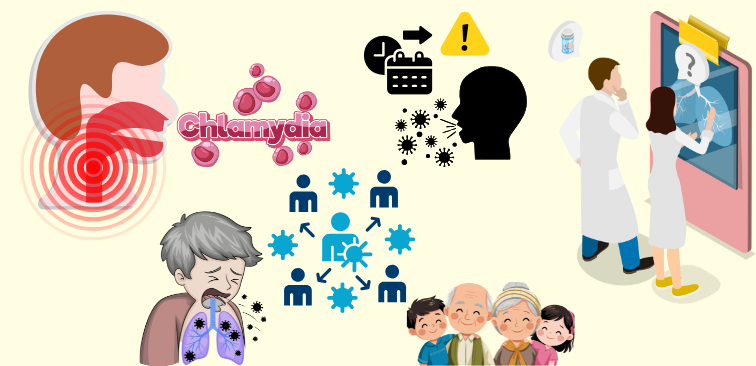
ここからは、病原菌や感染経路、症状の進行の特徴などを詳しくご説明いたしましょう。
1-1.病原菌について
細菌の一種であるクラミジア・ニューモニエ菌(肺炎クラミジア)が原因となって起こる呼吸器感染症です。
通常の細菌と比べて非常に小さく、自分だけでは増殖できずに宿主の細胞内でのみ増える「細胞内寄生菌」という特徴を持っています。
この菌が気道の細胞内に入り込んで増殖し、その過程で炎症を引き起こすことで肺炎が生じます。
1-2.一般的な肺炎との違い
市中肺炎(一般の社会生活を送る健康な人に発生する肺炎)の原因の一つとして知られており、肺炎全体の数%程度を占めるとされています。
症状が軽めで患者さんが普段どおり動けることも多いため、「歩行性肺炎」と呼ばれることもあります。
【参考文献】“Atypical Pneumonia: Clinical Features” by National Center for Biotechnology Information (NCBI Bookshelf)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430780/
1-3.症状の進行について
症状の進行は一般的な細菌性肺炎に比べてゆるやかで、経過が長引く傾向があります。
潜伏期間(感染から症状が出るまでの期間)は約2〜4週間と比較的長く、感染してもすぐには症状が現れません。
1-4.感染経路と集団感染のリスク
クラミジア・ニューモニエ菌は主にヒトからヒトへ飛沫感染(咳やくしゃみによるしぶき)で広がります。
閉鎖空間や人が密集する環境では感染リスクが高まり、学校のクラスや職場など集団生活の場で集団感染(アウトブレイク)が報告されています。
また、幅広い年齢層で感染する可能性がありますが、特に幼児〜学齢期のお子さんや高齢者で患者報告が多い傾向があります。
1-5.重症化のリスクがある人
喫煙者や慢性疾患がある方、免疫力が低下している方が感染すると重症化するリスクも指摘されています。
クラミジア・ニューモニエ肺炎自体は珍しい病気ではなく世界中で見られ、日本でも毎年一定数の患者報告があります。
ただし、症状が他の風邪や気管支炎と似て特異的でないため、見過ごされてしまう場合もあります。
長引く咳や微熱が続く場合には、この肺炎の可能性も考えて早めに医療機関を受診することが大切です。
1-6.その他のクラミジア肺炎との違い
なお、「クラミジア肺炎」という名称には、新生児が産道でクラミジア・トラコマチスに感染して起こる肺炎も含まれますが、鳥由来で重症化しやすいオウム病(Chlamydia psittaciによる肺炎)は別の疾患として区別されています。
【オウム病とは…鳥(オウムやインコなど)からうつる肺炎で、重症化しやすい特徴があります】
【参考情報】『クラミジア肺炎(オウム病を除く)』東京都感染症情報センター
https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/cpneumoniae/
2. クラミジア・ニューモニエ肺炎の症状

クラミジア・ニューモニエ肺炎の主な症状について説明します。
この病気は、一見すると他の風邪や肺炎と似た症状を示しますが、経過や程度にいくつか特徴があります。
典型的な症状としては、長引く咳が挙げられます。初期は軽い喉の違和感や乾いた咳から始まり、徐々に咳が悪化して数週間続くこともあります。
また発熱も見られますが、高熱(38℃以上)になるケースは多くはなく、微熱程度に留まることが一般的です。倦怠感(からだのだるさ)や軽い頭痛など全身の症状を伴うこともあります。
喉の痛みや声のかすれ、鼻水など、上気道炎に似た症状が現れることもあります。
こうした症状は他の一般的な気管支炎や肺炎でも見られますが、クラミジア・ニューモニエ肺炎の場合は症状が比較的長引く傾向にある点が特徴です。
多くの場合、症状は軽症から中等症程度で収まります。
しかし、高齢の方や持病のある方では、呼吸が苦しくなる(呼吸困難)など重症化する例も報告されています。そのため、単なる風邪と思っていても、咳が2週間以上続く場合は医療機関で検査を受けることが望ましいでしょう。
【参考情報】『肺炎クラミジア(Chlamydophila pneumoniae)』日本細菌学会
https://jsbac.org/pdf/bacteria/chlamydophila_pneumoniae.pdf
3. クラミジア・ニューモニエ肺炎の診断・検査

続いて、この肺炎の診断方法や検査について説明します。
クラミジア・ニューモニエ肺炎は、症状や胸部レントゲン所見だけでは他の肺炎と区別することが難しい病気です。
咳や発熱といった症状は非特異的であり、肺炎が起こってもレントゲン画像に特徴的なパターンが現れない場合もあります。そのため、臨床症状だけで確定診断することは容易ではありません。
確実に診断するには病原体やそれに対する抗体を検出する検査が必要です。
具体的には、喉や痰の検体から菌の遺伝子(DNA)を増幅して検出するPCR検査、菌の抗原を直接検出する方法、あるいは血液中のクラミジア抗体価を測定する血清学的検査があります。
特に血清中の抗体検査では、感染の初期と数週間後に採取した血液で抗体価の変化(有意な上昇)を確認することで、最近の感染であると診断できます。
ただし、これらの検査はいずれも専門的で、結果が出るまでに時間を要する場合があります。また、実際の診療現場では全ての肺炎患者さんにこうした検査を行うことは少なく、症状や経過から総合的に判断して治療を開始することが一般的です。
当院でもこうした検査には対応しておりません。クラミジア・ニューモニエ肺炎を含むいわゆる「非定型肺炎」が疑われるケースでは、必ずしも原因菌を特定せずとも有効な抗生物質を投与し経過を見る対応が取られます。
【参考情報】『肺炎クラミジア感染症の臨床』日本内科学会雑誌
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika1913/87/12/87_12_2516/_pdf
4. クラミジア・ニューモニエ肺炎の疑いがある時の対応と治療の流れ

職場や学校でクラミジア・ニューモニエ肺炎が疑われる症状が出た場合、どのように行動すればよいか分からないという方も多いかもしれません。
ここでは感染疑い者が出た時の初動対応、医療機関受診の目安、治療の基本、そして治療中の登校・出勤停止の目安について、詳しく解説していきます。
4-1. 感染が疑われた場合、職場・学校でまず行うこと
職場や学校でクラミジア・ニューモニエ肺炎が疑われる症状(長引く咳や微熱、倦怠感)が見られたら、まずは感染疑い者を速やかに周囲から離し、マスクを着用させましょう。本人に症状が軽くても感染力があるため、早めの医療機関受診を促します。
また、感染拡大防止のために教室やオフィスの換気、ドアノブや手すりなど共用部分の消毒を徹底します。感染疑い者と接触した人にも手洗いやマスク着用を再度指導し、特に集団感染が疑われる場合は、速やかに保健所などに相談し対応を進めましょう。
4-2. 医療機関への受診の目安
クラミジア・ニューモニエ肺炎は咳や微熱が長引くことが特徴です。
目安として、咳や微熱が3~4日以上続き、特に咳が悪化したり、倦怠感が強まる場合は肺炎の可能性があるため早めの受診を勧めます。
また、高齢者や持病のある方では症状が軽くても2日以上続けば受診を促しましょう。
受診時は、症状の経過を具体的に医師に伝えることが大切です。特に、いつ頃から症状が始まったか、症状が悪化したタイミングや周囲の感染状況(同じ症状の人の有無)などを伝えると診断の助けになります。
また、事前に医療機関に連絡をし、感染対策としてマスク着用を徹底しましょう。
4-3. 医師が行う治療の基本
クラミジア・ニューモニエ肺炎は医師の診断後、主に抗生物質による治療が行われます。
治療に使用される抗生物質は、一般的な細菌性肺炎とは異なり、クラミジア菌に効果のある特定の種類(マクロライド系など)が選択されます。具体的な薬剤の選定や投与期間については医師の判断に基づきます。
治療開始後、治療を受けると、多くの場合1週間程度で症状の改善が見られますが、個人差があります。
完全に咳が止まるまでには数週間かかることもあるため、症状が治まった後も医師の指示通りに薬を飲みきることが重要です。具体的な治療期間や復帰時期については、医師の指示に従ってください。
4-4. 治療中の生徒・社員の登校・出勤停止について
クラミジア・ニューモニエ肺炎は、学校保健安全法や労働安全衛生法に明確な出席停止や出勤停止の規定はありません。
しかし感染拡大防止の観点から、症状(特に咳や微熱)が続いている間は登校や出勤を控えることが望ましいでしょう。
一般的には、適切な治療を開始して症状が改善するまでの間、症状が改善し始めてから最低でも3日以上は登校や出勤を控えることが推奨されます。
具体的な期間は医師の診断を仰ぎ、必要に応じて診断書を提出してもらいましょう。復帰時は必要に応じて医療機関からの診断書や意見書の提出を求め、学校や職場と医療機関の連携を図ることが効果的です。
5. まとめ
クラミジア・ニューモニエ肺炎は、クラミジア菌による「非定型肺炎」の一つで、長引く咳や微熱が特徴です。
飛沫を介して感染し、学校や職場で集団発生が起こることもあります。
症状がおだやかなため「歩行性肺炎」とも呼ばれますが、放置すると長引いたり悪化する可能性があるため注意が必要です。
抗生物質による治療で改善しますが、咳や熱が続く場合には早めに医療機関を受診しましょう。予防には日頃の手洗いや咳エチケットの徹底が有効です。




