あばら骨が痛い。激しい咳が続くときはどうする?
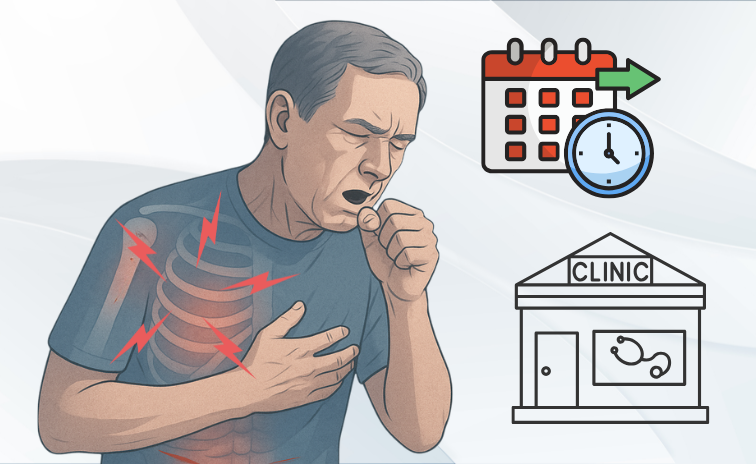
「咳くらいで病院に行くのは大げさかも…」と思っていませんか?
しかし、咳は思っている以上に体に負担をかける症状です。特に激しい咳が長期間続くと、筋肉や骨にダメージが蓄積し、日常生活に支障をきたすこともあります。
この記事では、咳によって骨や筋肉にどのようなダメージが起こるのか詳しく解説します。
1. 激しい咳がでると体全体に影響がでる

大人の場合、1回の咳で2~4kcalを消費すると言われています。
そのため咳が続くと体力が消耗し、疲労感や睡眠不足など、日常生活に支障をきたすことがあります。
【参考情報】環境再生保全機構『第39回日本小児臨床アレルギー学会共催 市民公開講座
「知りたいこどものアレルギー」レポート』
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/sukoyaka/column/202311_1
風邪などの一時的な咳では、喉や胸の痛みを感じることはあっても、筋肉痛やあばら骨の痛みはめったに起こりません。
しかし、激しい咳が長期間続くと、筋肉痛やあばら骨の痛みなどの全身症状が現れることがあります。
1-1.激しい咳による肋骨への影響
咳をするたびに、肋骨には強い負荷がかかります。
肋骨(あばら骨)は心臓や肺を守る役割があるため、健康な状態では丈夫な骨です。しかし、激しい咳が長引くことで負荷が蓄積し、肋骨にヒビが入ったり、疲労骨折を起したりすることがあります。
疲労骨折とは、一度では骨折が起こらない程度の弱い力が、同じ部位に繰り返し加わることで生じる骨折のことです。
【参考情報】日本骨折治療学会『疲労骨折』
https://www.jsfr.jp/ippan/condition/ip10.html
咳が長期間続く喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)などの慢性呼吸器疾患の場合は、激しい咳ダメージが蓄積するため、肋骨の疲労骨折リスクが高くなります。
【肋骨を疲労骨折した場合の症状】
初期段階では、運動時や体をひねる動作をしたときに、軽い違和感や鈍い痛みを感じることがあります。
また、押すと痛みを感じる「圧痛」や、軽い腫れが見られることもあります。
進行すると、深呼吸や咳、くしゃみをしただけでも激しい痛みを感じるようになります。
さらに悪化すると、安静にしていてもズキズキとした痛みが続き、寝返りや呼吸だけでも痛むなど、日常生活に支障が出ることがあります。
咳やくしゃみなどの軽い動作でも強い痛みを伴う場合は、早めの受診をおすすめします。
1-2.激しい咳による筋肉疲労と痛み
咳をすると、体中の様々な筋肉が連動し、負担がかかります。
・腹筋(特に腹直筋・外腹斜筋)
・肋間筋(肋骨と肋骨の間にある筋肉)
・横隔膜(胸と腹を隔てる呼吸の主役の筋肉)
・背筋・首の筋肉(咳の際の姿勢保持に関与する筋肉)
激しい咳をすると、これらの筋肉が瞬間的に強く収縮し、何度も同じ動作が繰り返されることで筋肉に負担が蓄積されていきます。
軽い筋肉痛程度であれば、湿布を貼るなどのセルフケアで回復します。
しかし、痛みが強い、または長引く場合は、肋骨骨折などの可能性も考えられます。
咳の原因を特定し対策するためにも、早めに医療機関を受診することが大切です。
1-3.その他
激しい咳が続くと、肋骨や筋肉以外にも様々な影響が出ることがあります。
①椎間板ヘルニアや腰痛の悪化
もともと椎間板ヘルニアを抱えている方や、腰痛持ちの方は、激しい咳によって症状が悪化する可能性があります。
咳をすると瞬間的に上体が前かがみになるため、背骨への負担が強くなり、「ぎっくり腰(急性腰痛症)」を起こす場合もあります。
②肋軟骨炎(ろくなんこつえん)
肋軟骨炎とは、肋骨と胸骨をつなぐ「肋軟骨」が炎症を起こすことで、胸の中央から脇の下あたりにかけて強い痛みが出る病気です。
原因は様々ですが、激しい咳による負荷が蓄積することも原因のひとつです。
心臓の痛みと間違われやすいのも特徴です。動作や深呼吸で痛みが増す場合は、肋軟骨炎が疑われます。
2.高齢女性は骨折のリスクが高い?
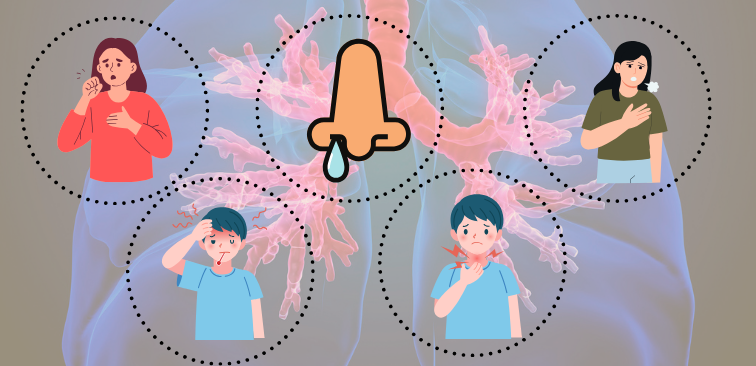
高齢の女性は、咳が続くことで疲労骨折を起こしやすい傾向があります。
その大きな理由のひとつが、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)の存在です。
骨粗鬆症とは、骨の密度(骨量)が減ってスカスカになり、もろくなる病気です。
特に閉経後の女性に多く、エストロゲン(女性ホルモン)の分泌が減少することで、骨が弱くなってしまいます。
【参考情報】日本整形外科学会『骨粗鬆症』
https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/osteoporosis.html
骨粗鬆症の方は転倒などの強い衝撃がなくても、軽い咳やくしゃみ、日常動作の繰り返しだけで骨折してしまう場合があります。
咳が長引くことで肋骨に負担が蓄積され、肋骨の疲労骨折を引き起こすリスクが高くなってしまいます。
骨粗しょう症による骨折リスクを下げるには、日頃の食事と運動、生活習慣の見直しが大切です。
・カルシウムを意識して摂る
・ビタミンDを摂取する
・適度な運動を習慣化する
・喫煙・過度な飲酒を避ける
・咳の原因疾患を治療し、負担を軽減する
高齢の場合は特に、骨折によってその後の生活の質が大きく低下することもあります。
「咳が止まらず、胸や脇腹が痛い」ということがあれば、早めに病院を受診しましょう。
【参考情報】Mayo Clinic『Osteoporosis』
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/osteoporosis/symptoms-causes/syc-20351968
3.激しい咳が止まらない。どうする?
咳が続いていても、「ただの風邪かもしれないし…」「そのうち治るだろう」と思って放置してしまう方もいるかもしれません。
しかし、これまでお伝えした通り、咳のわずかな衝撃でも蓄積することで、筋肉や骨に大きな負担がかかることがあります。特に、咳が2週間以上続く場合は、喘息などの呼吸器疾患が隠れているかもしれません。
早めに病院を受診して原因を突き止め、身体の負担を軽減することが大切です。
3-1.筋肉・骨の負担を軽減する方法
咳の衝撃から体を守るためには、筋肉や骨への負担を軽減する工夫が効果的です。
咳をする際は、壁や机に手をついたり、クッションを胸の前で抱えたりすることで、腰にかかる負担を少し減らすことができます。
また、姿勢を正しく保つことも重要です。
前かがみになると腹部や腰に負担がかかりやすいため、無理のない範囲で姿勢を整えましょう。
咳による筋肉痛や違和感がある場合は、湿布などで一時的に痛みを和らげることも可能です。
ただし、呼吸するだけで強い痛みがある、または痛みが長引く場合は、疲労骨折などの可能性もあります。
日常生活に支障をきたす場合は自己判断で済ませず、病院を受診しましょう。
3-2.咳止め薬では喘息を治せない
市販の咳止め薬を使っても、「咳が一時的に軽くなるだけ」で、根本的な治療にはなりません。
特に喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)などの慢性呼吸器疾患が原因の場合、症状を放置していると病気が進行し、激しい咳による骨や筋肉への負担が長期間続く恐れがあります。
このような場合、市販薬では対応できず、吸入薬や長期的なコントロール治療が必要になります。
また、喘息の中には「アスピリン喘息」と呼ばれるタイプもあり、市販の風邪薬や鎮痛薬に含まれる成分(アスピリン・ロキソプロフェンなど)で喘息症状が悪化することがあります。
そのため、自己判断で市販薬を使うのは避け、咳が続く場合は医療機関で正しい診断を受けることが重要です。
【参考情報】環境再生保全機構『アスピリン喘息』
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/knowledge/aspirin.html
3-3.激しい咳が続くときは呼吸器内科へ
咳が長引いてつらいときは、一般内科よりも呼吸器内科を受診するのがおすすめです。
呼吸器内科では、喘息・COPD・肺炎などの咳の原因となる病気を正確に診断し、適切な治療を行うことができます。
また、長引く咳の他に胸部や腹部の痛みもある場合、「呼吸器内科に行くべきか、整形外科に行くべきか迷う」という方もいるのではないでしょうか。
もちろん、すでに肋骨の疲労骨折や強い筋肉痛が疑われる場合には、整形外科の診察が必要になることもあります。
しかし、咳の原因が喘息やCOPDなどの慢性呼吸器疾患である場合、いくら骨や筋肉を治療しても、咳を止めなければ根本的な改善にはなりません。
まずは呼吸器内科で咳の原因を明らかにし、必要に応じて整形外科へ紹介を受けるという流れが良いでしょう。
4.おわりに
咳は風邪の一症状として軽く見られがちですが、実は肋骨の疲労骨折など、全身に思わぬ負担をかけることがあります。
特に咳が2週間以上続く場合は、喘息やCOPDなどの慢性呼吸器疾患が隠れていることもあります。
まずは呼吸器内科で咳の原因を明らかにし、必要に応じて整形外科へ紹介を受けるなど、適切な対処をしましょう。




