更年期の不調だと思っていたら実は貧血!50代女性が知るべき貧血の見分け方

「最近めまいがひどくて、疲れやすい」「更年期だから仕方ない」と諦めていませんか?
実は、更年期特有の症状だと思っていた不調が、貧血によるものかもしれません。
50代前後の女性は、女性ホルモンの変化だけでなく、貧血の症状も重なりやすい年代です。
この記事では、更年期症状と貧血の違いや見分け方について詳しく解説いたします。
適切な診断と治療を受けることで、つらい症状から解放される可能性があります。
1. 更年期症状と貧血、どちらも同じような症状が現れます
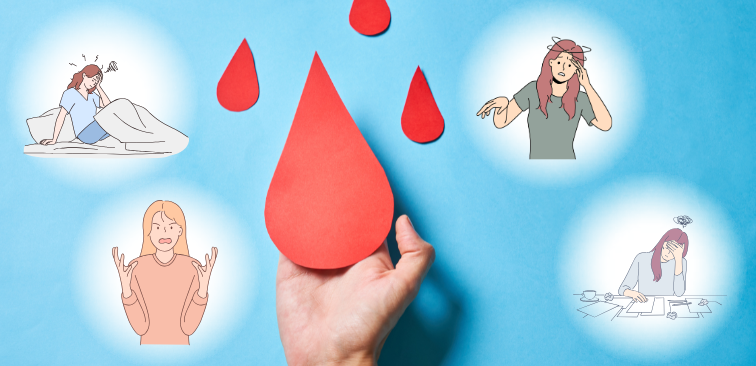
更年期の不調と貧血の症状は、非常によく似ているため、多くの女性が見分けに困っています。
1-1. 更年期症状の特徴
更年期は、閉経の前後約5年ずつの10年間を指し、一般的には45~55歳頃に現れます。
卵巣機能の低下による女性ホルモンの減少が主な原因で、「疲れやすい」「肩こり・腰痛・手足の痛み」「汗をかきやすい」「腰や手足が冷えやすい」「怒りやすく、すぐイライラする」「寝付きが悪い、眠りが浅い」などの様々な症状が現れます。
【参考情報】『更年期症状で仕事をあきらめないために 早めに婦人科とつながろう』厚生労働省
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/health/menopause.html
【参考文献】“Menopause symptoms and relief” by Office on Women’s Health, U.S. Department of Health and Human Services
https://womenshealth.gov/menopause/menopause-symptoms-and-relief
1-2. 貧血の症状の特徴
貧血は、血液中の赤血球の中にあるヘモグロビンが少なくなった状態です。
立ちくらみ、めまい、頭痛、胸の痛み、息切れ、動悸、疲労感、倦怠感、肌荒れなどの症状が現れます。
日本女性の40%、特に月経のある20代~40代の女性の約65%が「貧血(鉄欠乏性)」もしくは「かくれ貧血」の状態にあるとされています。
【参考情報】『貧血・かくれ貧血』厚生労働省
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/health/anemia.html
【参考文献】“Iron-deficiency anemia” by Office on Women’s Health, U.S. Department of Health and Human Services
https://womenshealth.gov/a-z-topics/iron-deficiency-anemia
1-3. 症状が重なる理由
更年期症状と貧血の症状が重なる理由は、どちらも体の基本的な機能に影響を与えるためです。
女性ホルモンの減少は自律神経系に影響を与え、貧血は酸素を全身に送る機能に影響を与えます。そのため、「疲れやすい」「めまい」「頭痛」「イライラ」などの症状が共通して現れるのです。
2. 貧血の種類と原因を知って、正しく理解しましょう

50代女性に多い貧血には、主に「鉄欠乏性貧血」と「慢性疾患に伴う貧血」があります。
2-1. 鉄欠乏性貧血とは
鉄欠乏性貧血は、体内の鉄分が不足することで起こる最も一般的な貧血です。
ヘモグロビンは鉄分によって構成されているため、鉄分が不足するとヘモグロビンの量も減ってしまい、体内が酸欠状態になります。
女性は毎月の生理で出血するため、血液に含まれる鉄分が失われ、それに対応するだけの鉄分の摂取が足りないことで発生します。
【参考情報】『貧血』女性の健康推進室 ヘルスケアラボ
https://w-health.jp/monthly/anemia/
2-2. 慢性疾患に伴う貧血とは
慢性疾患に伴う貧血は、関節リウマチ、がん、慢性腎疾患、炎症性腸疾患などの慢性的な病気が原因で起こる貧血です。
これらの疾患があると、体内で炎症が続くため、鉄の利用がうまくいかなくなったり、赤血球の産生が低下したりして貧血が起こります。
【参考文献】“Anemia in postmenopausal women: dietary inadequacy or non-dietary factors” by Agricultural Research Service, USDA
https://www.ars.usda.gov/research/publications/publication/?seqNo115=264084
2-3. 50代女性特有の貧血の原因
50代女性の貧血の原因として、以下のようなものが考えられます。
まず、子宮筋腫や子宮腺筋症による月経過多があります。
これらの疾患は40代~50代に多く見られ、月経量が増えることで鉄分が大量に失われます。また、胃腸の病気による慢性的な出血も原因となることがあります。
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、大腸がんなどによる少量の出血が続くと、気づかないうちに貧血が進行することがあります。
【参考文献】“Vaginal or uterine bleeding” by MedlinePlus, U.S. National Library of Medicine
https://medlineplus.gov/ency/article/007496.htm
2-4. 食生活の変化も影響
更年期を迎えると、体重管理への意識から食事制限をする女性も多くなります。
しかし、過度な食事制限は鉄分やタンパク質の摂取不足を招き、貧血の原因となることがあります。
特に、肉類を避ける傾向がある場合、吸収率の高いヘム鉄の摂取が不足しがちになります。
3. 更年期症状と貧血の見分け方のポイント

更年期症状と貧血を見分けるためには、症状の現れ方や特徴を詳しく観察することが大切です。
3-1. 症状の現れ方の違い
更年期症状は、ホットフラッシュ(のぼせ・ほてり)が特徴的で、急に顔や上半身が熱くなり、汗をかくことが多いです。
一方、貧血では、立ち上がった時のめまいや立ちくらみが特徴的で、階段を上った時の息切れや動悸が強く現れます。
また、更年期症状は時間帯によって症状の強さが変わることが多いのに対し、貧血の症状は一日を通して持続的に現れることが多いです。
【参考文献】“Menopause symptoms? It could be a copycat” by Mayo Clinic
https://mcpress.mayoclinic.org/menopause/menopause-symptoms-it-could-be-a-copycat/
3-2. 身体的な変化の違い
貧血では、爪の変化が見られることがあります。
爪が薄くなる、反り返る、割れやすくなるなどの変化が現れます。また、顔色が青白くなったり、まぶたの裏(結膜)が白っぽくなったりします。
更年期症状では、このような明確な身体的変化は見られにくいことが特徴です。
3-3. 症状の改善方法の違い
更年期症状は、ホルモン補充療法や漢方治療により改善が期待できます。
一方、貧血の症状は、鉄分補給や原因疾患の治療により改善します。
セルフケアとして、更年期症状は規則正しい生活リズムやストレス管理が効果的ですが、貧血の場合は鉄分を多く含む食事の摂取や、原因となる出血を止めることが重要です。
4. 貧血の検査と診断について詳しく知りましょう

貧血の正確な診断のためには、適切な検査を受けることが重要です。
4-1. 基本的な血液検査項目
貧血の診断に必要な基本的な血液検査項目には、以下があります。
ヘモグロビン値は、血液中の酸素を運ぶ赤い色素の量を測定し、女性では12g/dL未満で貧血と診断されます。
赤血球数は、血液中の赤血球の個数を数え、ヘマトクリット値は、血液中に占める赤血球の割合を示します。
4-2. 鉄欠乏性貧血の特殊検査
鉄欠乏性貧血を診断するための特殊な検査項目があります。
血清鉄は、血液中の鉄分の量を測定し、鉄欠乏性貧血では低下します。
総鉄結合能(TIBC)は、血液中で鉄を運ぶタンパク質の能力を測定し、鉄欠乏性貧血では上昇します。
最も重要なのは血清フェリチン値で、体内の鉄貯蔵量を示し、鉄欠乏性貧血では著明に低下します。
4-3. 慢性疾患に伴う貧血の鑑別
慢性疾患に伴う貧血と鉄欠乏性貧血を鑑別するためには、血清フェリチン値が重要な指標となります。
慢性疾患に伴う貧血では、炎症により血清フェリチン値が正常または高値を示すことが多いのに対し、鉄欠乏性貧血では明らかに低値を示します。
4-4. 原因を調べるための追加検査
貧血の原因を特定するために、追加の検査が必要な場合があります。
消化器系の出血を調べるために、便潜血検査や胃内視鏡検査、大腸内視鏡検査を行うことがあります。
婦人科疾患による出血を調べるために、経腟超音波検査や子宮内膜の検査を行うこともあります。
また、慢性疾患の有無を調べるために、関節リウマチの検査や腎機能検査なども行われる場合があります。
当院で、女性の貧血を診療する場合は、内視鏡検査のために消化器内科、婦人科疾患の診察のために婦人科への紹介を併せて実施させていただきます。
5. 治療法と日常生活での改善方法

貧血の治療は、その種類や原因によって異なりますが、適切な治療により症状の改善が期待できます。
5-1. 鉄欠乏性貧血の治療
鉄欠乏性貧血の治療の基本は、鉄剤の内服です。
医師から処方される鉄剤を、通常3~6カ月間服用します。
鉄剤は空腹時に服用すると吸収が良くなりますが、胃腸症状が現れる場合は食後に服用することもあります。
重症の場合や内服ができない場合は、静脈内への鉄剤投与を行うこともありますが、当院では対応できません。
5-2. 慢性疾患に伴う貧血の治療
慢性疾患に伴う貧血の治療は、まず原因となる慢性疾患の治療が最優先となります。
関節リウマチであれば抗リウマチ薬、慢性腎疾患であれば腎機能の保護、がんであれば抗がん治療などが行われます。
原因疾患の治療と並行して、必要に応じて鉄剤やエリスロポエチン製剤(赤血球産生を促進する薬)が使用されることもありますので、高次医療機関へご紹介いたします。
5-3. 食事療法のポイント
貧血の改善には、食事からの鉄分摂取も重要です。
鉄分には「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」の2種類があり、肉・魚などに含まれるヘム鉄の吸収率は25%ほど、野菜・豆・穀物・海藻などに含まれる非ヘム鉄の吸収率は3~5%ほどです。
効率的に鉄分を摂取するためには、レバー、赤身肉、魚、貝類などのヘム鉄を多く含む食品を積極的に摂取しましょう。
5-4. 鉄分の吸収を高める工夫
鉄分の吸収を高めるためには、ビタミンCを多く含む食品と一緒に摂取することが効果的です。
柑橘類、いちご、キウイフルーツ、ブロッコリー、ピーマンなどがおすすめです。
一方、緑茶、コーヒー、紅茶に含まれるタンニンや、穀物に含まれるフィチン酸は鉄の吸収を阻害するため、鉄分を多く含む食事と同時に摂取することは避けた方が良いでしょう。
5-5. 生活習慣の改善
貧血の改善には、生活習慣の見直しも大切です。
十分な睡眠をとり、適度な運動を心がけることで、体内の血液循環が改善され、酸素の運搬効率が高まります。
ただし、貧血の症状が強い時期は、激しい運動は避け、散歩などの軽い運動から始めることが大切です。また、ストレスも貧血の症状を悪化させる要因となるため、リラクゼーションや趣味などでストレス解消を心がけましょう。
6. どの科を受診すべきか迷った時の判断基準

更年期症状と貧血の症状が重なる50代女性は、どの診療科を受診すべきか迷うことが多いでしょう。
6-1. まずは内科を受診する場合
疲労感、めまい、息切れ、動悸などの症状が主体で、明らかな婦人科的な問題(月経過多など)がない場合は、まず内科を受診することをおすすめします。
内科では、血液検査により貧血の有無や種類を診断し、必要に応じて消化器内科や血液内科などの専門科に紹介してもらえます。
また、慢性疾患に伴う貧血の可能性がある場合も、内科での総合的な診察が有効です。
6-2. 婦人科を受診する場合
月経過多、不正出血、下腹部痛などの婦人科的な症状がある場合は、婦人科を受診しましょう。
特に、月経量が多い、月経期間が長い、月経以外の出血があるなどの症状がある場合は、子宮筋腫や子宮内膜症などの疾患による貧血の可能性があります。
婦人科では、経腟超音波検査や子宮内膜の検査により、原因疾患の診断と治療を行います。
【参考情報】『女性の貧血について~婦人科の視点から』成田赤十字病院
https://www.narita.jrc.or.jp/department/sanfujinka/josei_hinketsu.html
6-3. 血液内科を受診する場合
一般的な鉄欠乏性貧血の治療を行っても改善しない場合や、血液検査で異常な値が認められる場合は、血液内科での専門的な診察が必要になることがあります。
血液内科では、より詳細な血液検査や骨髄検査により、血液疾患による貧血の可能性を調べます。
6-4. 複数の診療科の連携
実際には、更年期症状と貧血の両方の要因が関わっている場合も多く、複数の診療科での連携した治療が必要になることがあります。
内科で貧血の診断と治療を受けながら、婦人科で更年期症状の治療を受けるなど、総合的なアプローチが効果的です。
かかりつけ医がいる場合は、まずはかかりつけ医に相談し、適切な診療科への紹介を受けることをおすすめします。
7.おわりに
更年期の不調だと思い込んでいた症状が、実は貧血によるものかもしれません。
50代女性は、女性ホルモンの変化と貧血の両方が重なりやすい年代です。
めまいや疲労感、息切れなどの症状が続く場合は、更年期症状として諦めずに、まずは血液検査を受けて貧血の有無を確認することが大切です。
適切な診断と治療により、つらい症状から解放され、より快適な毎日を送ることができるでしょう。
症状が気になる方は、ぜひお近くの医療機関にご相談ください。




