気管支炎にはストレスが影響するのか?

気管支炎は、咳や痰、発熱などの症状が現れる呼吸器の病気です。
お子さまや高齢の方は重症化しやすく、日常生活にも大きな影響を及ぼします。
近年、ストレスが気管支炎の発症や症状の悪化に関係していることがわかってきました。
この記事では、気管支炎の種類や症状などについてご説明いたします。
1.気管支炎ってどんな病気?

気管支炎とは、呼吸をするときに空気が通る「気管支」という部分に炎症が起こる病気です。
気管支は、空気を肺に運ぶ大切な通り道です。
気管支がウイルスや細菌、タバコの煙や大気汚染、アレルギーなどの刺激によって炎症を起こした場合、咳や痰、発熱などの症状が現れます。
急性と慢性の2つに分類されますが、どちらの気管支炎も日常生活に大きな影響を与えます。
例えば、気管支炎になると夜間に咳が止まらず眠れなくなったり、外出や仕事、学校生活に支障をきたしたりすることも少なくありません。
また、気管支炎はほかの呼吸器疾患と症状が似ているため、自己判断で放置してしまう方もいらっしゃいます。
しかし、適切な治療を行わなかったり、生活管理を怠ったりした場合、症状が長引き重症化することがあります。
そのため、気になる症状がある場合には、呼吸器内科をはじめとする医療機関への早めの受診が大切です。
1-1.急性気管支炎
急性気管支炎は、風邪をひいたあとやインフルエンザなどの感染症が流行する時期に多く見られます。
原因のほとんどはウイルス感染ですが、細菌感染が原因となることもあります。
急性気管支炎の大部分はウイルス感染が原因で、インフルエンザウイルスや風邪ウイルスなどが気道(気管や気管支)の粘膜に感染します。
ウイルスが体内に入ると、気管支の表面にある細胞(上皮細胞)に侵入し、そこで増殖します。
その過程で、細胞が壊れたり、免疫反応が起こったりして、気管支の粘膜に炎症が生じます。
この炎症によって、咳や痰、のどの痛みなどの症状が現れます。
細菌が原因となることもあり、主にマイコプラズマや百日咳菌、肺炎球菌など特定の細菌が原因です。
最初の症状は、喉の痛みや鼻水、微熱など、一般的な風邪とよく似ています。しかし、数日経つと咳が強くなり、痰が絡むようになります。
咳は昼夜を問わず続くことが多く、夜間に悪化することもあります。この状態が続くと、睡眠不足や倦怠感を感じやすくなります。
急性気管支炎の咳は、体力を消耗させるだけでなく、胸や腹筋に痛みを感じることもあります。激しい咳によって生じる肋骨骨折が、胸痛につながることもあります。
また、咳が長引くことで、日常生活に支障をきたし、仕事や学業に集中できなくなる方も少なくありません。
とくにお子さまの場合、気管支が細くて弱いため、炎症が広がりやすく、喘鳴(ヒューヒュー、ゼーゼーという呼吸音)が出やすい傾向があります。
お子さまの呼吸が苦しそうだったり、顔色が悪かったりする場合は、すぐに医療機関を受診してください。
急性気管支炎の治療は、主に対症療法です。
ウイルスが原因の場合、抗菌薬は効果がないため、咳止めや去痰薬、解熱鎮痛薬などで症状を和らげます。
十分な休養と水分補給、栄養バランスの良い食事が回復のポイントです。細菌感染が疑われる場合は、医師の判断で抗菌薬が処方されることもあります。気管支炎の病態で、咳が長期に及ぶ場合は、細菌感染の可能性も高く、当院では抗菌薬を用いることがあります。
1-2.慢性気管支炎
慢性気管支炎は、長期間にわたって咳や痰が続く病気です。
1年のうち3か月以上、2年以上連続して症状がみられる場合に診断されます。
慢性気管支炎の主な原因は、長年にわたる喫煙や大気汚染、受動喫煙、アレルギー体質などです。
とくに喫煙は、慢性気管支炎の最大のリスク要因だと言えます。
タバコの煙に含まれる有害物質は気管支の粘膜を傷つけ、炎症を慢性的に引き起こします。これにより、気管支の防御機能が低下し、痰が増えたり、咳が長引いたりします。
症状は、朝方や寒い時期に悪化しやすいのが特徴です。
咳や痰が続くだけでなく、進行すると息切れや呼吸困難を感じるようになります。
重症化すると、肺の機能が低下し、日常生活に大きな支障をきたすことも否定できません。
また、慢性気管支炎は「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」の一部として分類されることもあります。
慢性閉塞性肺疾患は進行性の病気で、早期発見と治療が重要です。
そのため、慢性的な咳や痰が続く場合は、早めに呼吸器内科をはじめとする医療機関への受診を検討しましょう。適切な検査と治療を受けることができます。
慢性気管支炎の治療の基本は、禁煙と生活習慣の改善です。
気管支拡張薬や去痰薬、吸入薬などが使われることもあります。重症の場合は、酸素療法や呼吸リハビリテーションが必要になることもあるでしょう。
【参照文献】日本内科学会雑誌『慢性気道感染症の病態と治療戦略』
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/98/9/98_2300/_pdf
【参考情報】Mayo Clinic『Bronchitis』
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bronchitis/symptoms-causes/syc-20355566
2.主な症状
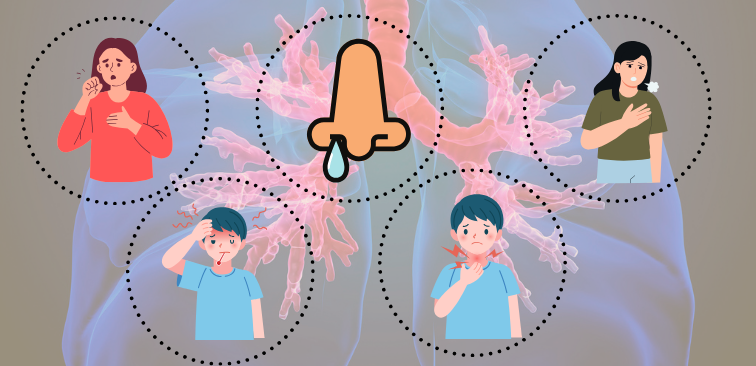
ここからは、気管支炎の症状について詳しくご説明しましょう。気管支炎の主な症状は、咳、痰、発熱、鼻水、喉の痛み、倦怠感などです。
これらの症状は、急性気管支炎と慢性気管支炎のどちらにも共通してみられますが、症状の現れ方や持続期間には違いがあります。
急性気管支炎の場合、最初は乾いた咳が続きますが、数日経つと痰が絡む湿った咳に変わります。
咳は昼夜を問わず続き、夜間に悪化することが多いです。発熱や鼻水、喉の痛みなど、風邪に似た症状もよく見られます。
多くの場合、1〜2週間で症状は改善しますが、咳だけが3週間以上続くこともあります。
慢性気管支炎の場合は、咳や痰が長期間続くのが特徴です。
とくに朝方や寒い時期に症状が強くなり、痰の量が増えたり、色が変わったりすることもあります。
進行すると、階段の上り下りや軽い運動でも息切れを感じるようになります。胸の痛みや喉の違和感、全身のだるさなども現れることがあります。
また、前述のとおり、小さなお子さまは気管支が細くて弱いため、炎症が広がりやすく、重症化することがあります。
とくに生後6か月未満のお子さまや、もともと心臓や肺に病気を持つお子さま、早産児、免疫力が低下しているお子さまは、気管支炎から細気管支炎や肺炎に進行しやすく、入院治療が必要になることもあります。
お子さまの咳が長引いたり、呼吸が苦しそうな様子が見られたりした場合は、早めに医療機関を受診してください。
夜間や休日でも、呼吸困難や顔色の悪化、意識がもうろうとしている場合は、迷わず救急車を呼びましょう。
3.ストレスが与える影響

ストレスは、現代社会に生きる私たちにとって避けて通れないものです。
仕事や家事、育児、人間関係、将来への不安など、日常のさまざまな場面でストレスは生じます。
ここからは、このようなストレスがからだにどのような影響を与えるのか、気管支炎との関係について詳しくご説明しましょう。
ストレスを感じると、からだは「戦うか逃げるか」という緊張状態になります。
この状態は自律神経のうち交感神経が優位になることで起こります。交感神経が優位になると、心拍数や血圧が上がり、呼吸も浅く速くなります。
この反応は本来、危険から身を守るための生理的な仕組みですが、ストレスが長期間続くと、からだのさまざまな機能に悪影響を及ぼします。
ストレスによる最大の問題は、免疫力の低下です。
ストレスを感じている状態が続くと、「コルチゾール」というストレスホルモンが長期間分泌されます。
コルチゾールは、短期間であれば炎症を抑えたり、エネルギーを確保したりする役割を果たしますが、長期間にわたり高値が続くと、逆に免疫細胞である白血球の働きを弱めてしまいます。
その結果、ウイルスや細菌に対する抵抗力が落ち、気管支炎をはじめとする感染症にかかりやすくなったり、いったんかかった病気が治りにくくなったりするのです。
また、ストレスは自律神経のバランスを崩します。
自律神経は呼吸や心拍、消化、体温調節など、意識しなくてもからだをコントロールしている大切な神経です。
ストレスが続くと交感神経が優位になり、気管支が収縮しやすくなったり、咳が出やすくなったりします。
とくに気管支がもともと弱い方や、喘息の既往がある方は、ストレスが発作の引き金になることもあります。
ストレスは精神的なものだけでなく、物理的なストレスも含まれます。
例えば、大気汚染や冷たい空気、たばこの煙、アレルゲン(花粉やダニなど)、香水や化学物質の刺激なども、からだにとってはストレスとなり、気道の過敏性を高める要因となります。
これらの物理的ストレスも、気管支炎や喘息の悪化に関与していることがわかっています。
さらに、ストレスは睡眠の質にも大きな影響を与えます。
夜に不安や緊張を感じて眠れなくなると、体力や免疫力がさらに低下し、気管支炎の症状が悪化したり長引いたりする悪循環に陥ることがあります。
睡眠不足が続くと、からだは十分に回復できず、感染症への抵抗力も弱まってしまいます。
ストレスによる影響は、患者さんの生活の質(QOL)にも大きく関わります。
【QOL・・・Quality of Life(クオリティ・オブ・ライフ)の略で、日本語では「生活の質」「人生の質」「生命の質」などと訳されます。これは、ある人がどれだけ人間らしい生活や自分らしい生活を送り、人生に幸福を見出しているかを評価する指標のことです。】
仕事が忙しくて休めない、家族の介護や育児で自分の時間が持てないなど、ストレスを抱えながら治療を続けている方は多くいらっしゃいます。
ストレスがたまると、どうしても体調管理が疎かになりがちです。
食事が偏ったり、運動不足になったり、睡眠時間が短くなったりすることで、さらに免疫力が低下し、気管支炎の症状がなかなか改善しないという悪循環に陥ることもあります。
また、ストレスは炎症反応そのものを強めることもあります。
精神的ストレスが強いと、体内で炎症性物質(サイトカインなど)が増加し、気道の炎症が悪化しやすくなります。これは、喘息や慢性気管支炎の患者さんで特に顕著です。
ストレスによって症状の悪化や気管支炎の治りが遅くなったりするなどの影響があると考えられているため、日々のストレスケアがとても重要です。
ストレスを完全になくすことは難しいですが、適度な休息、良質な睡眠、バランスのとれた食事など、できることから始めてみましょう。
ストレスが気管支炎の症状を悪化させるメカニズムは複雑ですが、主に以下のような流れが考えられます。
・精神的・物理的ストレスが継続的にかかる
・自律神経のバランスが崩れ、交感神経が優位になる
・気道が収縮しやすくなり、咳や息苦しさが増す
・ストレスホルモンの影響で免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなる
・炎症性物質が増加し、気道の炎症が悪化する
・睡眠不足や疲労の蓄積で、さらに症状が長引く
このような悪循環を断ち切るためにも、ストレス対策や生活習慣の見直しがとても大切です。
症状がなかなか改善しない場合は、ストレスの影響も考慮しながら、生活全体を見直すことが重要です。
ストレスと気管支炎の関係を理解し、日々のストレスケアを意識することで、症状の予防や改善につなげていきましょう。
【参照文献】厚生労働省『ストレスとは:ストレス軽減ノウハウ|こころの耳』
https://kokoro.mhlw.go.jp/nowhow/nh001/
4.気管支炎の予防にはストレス発散が大切

気管支炎を予防し、症状を軽くするためには、ウイルスや細菌の感染を防ぐことはもちろん、ストレスをため込まないことが非常に重要です。
ストレスをうまく発散することで、免疫力を高め、からだの回復力を保つことができます。
ストレス発散の方法は人それぞれですが、ここでは多くの方におすすめできる「運動」と「お風呂にゆっくり浸かる」ことについて、より具体的にご紹介しましょう。
4-1.運動をする
運動は、ストレス発散だけでなく、健康維持や免疫力アップにも効果的です。
運動をすると、脳内で「エンドルフィン」や「セロトニン」といった幸福感やリラックスをもたらすホルモンが分泌され、気持ちが前向きになります。
運動後の爽快感や達成感は、ストレスを和らげる大きな力になります。
運動といっても、激しいスポーツをする必要はありません。
ウォーキングやストレッチ、ヨガ、体操、軽いジョギングなど、無理なく続けられるものを選びましょう。
日常生活のなかで、エレベーターの代わりに階段を使う、バス停をひとつ手前で降りて歩く、家事をしながらからだを動かすなど、ちょっとした工夫でも十分効果があります。
また、運動は呼吸器の機能を高める効果もあります。呼吸筋が鍛えられることで、咳や痰の排出がしやすくなり、気管支炎の予防や回復に役立ちます。
ただし、気管支炎の症状が強いときや、発熱、息切れがある場合は無理をしてはいけません。
また、心臓や呼吸器などに持病がある方、高齢者の方は、必ず主治医と相談の上、適切なレベルの運動を行うようにしましょう。
ご自身の体調や体力に合わせて、無理のない範囲で続けることが大切です。
運動を習慣化することで、ストレスに強いからだと心を作ることができます。ご自身に合った運動を見つけ、楽しみながら続けてみましょう。
4-2.お風呂にゆっくり浸かる
お風呂に入ることは、心身のリラックスにとても効果的です。
温かいお湯にゆっくり浸かることで、全身の血行が良くなり、筋肉の緊張がほぐれ、疲れがとれやすくなります。
また、入浴中は副交感神経が優位になり、心拍数や血圧が下がってリラックスしやすい状態になります。
さらに、お風呂の蒸気を吸い込むことで、気道の粘膜が潤い、咳や痰の症状が和らぐこともあります。
とくに乾燥した季節や、エアコンの効いた部屋で過ごすことが多い方には、入浴による加湿効果もおすすめです。
入浴時には、お気に入りの入浴剤やアロマオイルを使うと、よりリラックス効果が高まります。好きな音楽を聴いたり、照明を少し暗くしたりするのも良いでしょう。
ただし、発熱がある場合や、息苦しさ、動悸、めまいなどの症状がある場合、また心臓や呼吸器などに基礎疾患がある方は、入浴によるからだへの負担が大きくなることがあります。
そのため、入浴をする際は必ず主治医と相談し、体調に合わせて無理のない範囲で行うようにしましょう。
入浴後は水分補給を忘れずに行い、からだが冷えないように気をつけてください。
長湯を避け、40度前後のぬるめのお湯で10〜15分程度浸かるのが理想的です。
5.おわりに
気管支炎は、咳や痰、発熱などの症状が続くため日常生活に大きな影響を与えます。
また、気管支炎の症状が長引くことで、不安や焦りを感じる方も少なくありません。
こうした精神的なストレスがさらに免疫力を低下させ、症状の悪化や治りの遅れを招くことも否定できません。
気管支炎の症状が長引いたり、生活に支障をきたしたりする場合は、早めに呼吸器内科を受診しましょう。




