喘息などの呼吸器疾患の治療で使う「吸入薬」とは
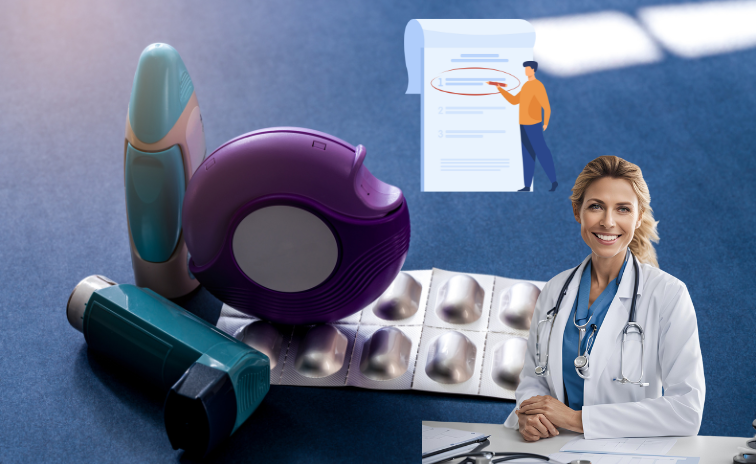
喘息をはじめとする呼吸器疾患の治療にとって、吸入薬はとても重要な役割があり、欠かせない治療薬だと言えます。
吸入薬は、気道に直接薬を届けることで、症状を素早く改善し、副作用も少ない治療方法です。
長期管理薬として日常的に使うことで発作を防ぎ、また発作が起きた際にはすぐに効果を実感でき、症状を楽にします。
この記事では、吸入薬の種類や使用方法、使用に関する注意点、日常生活で気をつけたいことについてご説明いたします。
1.吸入薬を使用する目的について

吸入薬の主な目的は、喘息発作を予防し、気道の炎症を抑えることです。
喘息は長期的に治療が必要な慢性的な病気であるため、適切に管理することが必要です。そのため吸入薬は、単に症状を和らげるだけではなく、根本的な治療手段として位置づけられています。
また、根本治療に加えて発作が起きた際に速やかに症状を緩和する役割もあります。
さらに、吸入薬は、飲み薬と比べて少ない量で高い効果が得られ、からだ全体への負担が少ないというメリットもあります。
ここからは、具体的な吸入薬についてご紹介しましょう。
1-1.長期管理薬(コントローラー)
長期管理薬は、喘息発作を未然に防ぐために、毎日継続して使用する薬です。これらの薬を日常的に使うことで、気道の炎症を抑え、発作の頻度や重症度を減らすことができます。
【参考情報】Mayo Clinic 『Corticosteroid (inhalation route)』
https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/corticosteroid-inhalation-route/description/drg-20070533
主な長期管理薬の役割と効果
長期管理薬では、とくに「吸入ステロイド薬」が使用されます。吸入ステロイド薬は、気道の炎症を鎮める効果があり、以下のような効果が期待できます。
・気道過敏性を改善:炎症が抑えられることで気道が落ち着き、刺激に対する過敏さが改善されます。
・発作の予防:炎症を減らすことで、発作の頻度と重症度が軽くなります。
このように、長期管理薬は喘息のコントロールを良好に保つための重要な役割を果たしています。
長期管理薬を使用する際のポイント
長期管理薬の効果を最大限に引き出すためには、以下のような点に注意することが大切です。
1.症状がなくても継続使用
発作が起きていない時や症状が安定している時でも、長期管理薬を毎日続けることが重要です。これにより、気道の状態が安定し、長期的な喘息管理が可能になります。
2.使い続けることで薬の効果が安定
吸入ステロイド薬は、全身への影響が少なく、長期間の使用でも安全性が高いとされています。薬を始めてすぐに効果が見られたとしても、医師の指示に従い、継続して使用することが必要です。
3.症状が安定すれば、減薬も可能
コントロールが良好な状態が1年前後続けば、医師と相談のうえ、薬の量や種類を徐々に減らしていくこともできます。
4.効果が見られない場合は主治医に相談
もし2〜4週間使用しても症状が改善しない場合や、新たに症状が出た場合は、必ず主治医に相談しましょう。
代表的な長期管理薬には以下のようなものがあります。
1. 副腎皮質ステロイド薬
吸入ステロイド薬(吸入薬)
喘息治療の中心的な薬です。薬剤を吸入することで、直接肺に届け、気道の炎症を抑えます。
商品例:アズマネックス®、オルベスコ®、キュバール®、パルミコート®、フルタイド®など
経口ステロイド薬(飲み薬)
全身に作用するステロイドで、強力な抗炎症効果があります。副作用には十分に注意が必要です。
商品例:プレドニゾロン®、プレドニン®、メドロール®、リンデロン®、セレスタミン®(抗ヒスタミン薬との合剤)
2. 長時間作用性β2刺激薬
交感神経を刺激して気管支を拡げる作用があり、吸入ステロイド薬との併用が基本です。
商品例:セレベント®(吸入薬)、ホクナリンテープ®(貼り薬)
3. 吸入ステロイド薬/長時間作用性β2刺激薬配合剤(吸入薬)
1つの薬剤で気道の炎症を抑える作用と気管支拡張の作用を持ちます。
商品例:アドエア®、シムビコート®、フルティフォーム®、レルベア®
4. ロイコトリエン受容体拮抗薬(飲み薬)
ロイコトリエンという化学伝達物質の働きをブロックし、気管支の収縮を抑えます。
商品例:オノン®(プランルカスト)、キプレス®、シングレア®(モンテルカスト)
5. テオフィリン徐放製剤(飲み薬)
ゆっくりと溶けることで作用時間が長く、気管支を拡げる効果があります。軽い抗炎症作用もあるとされています。
商品例:スロービッド®、テオドール®、テオロング®
6. 長時間作用性抗コリン薬(吸入薬)
アセチルコリンという物質の作用を抑制することで、気管支の収縮を防ぎます。
商品例:スピリーバレスピマット®
7. ロイコトリエン受容体拮抗薬以外の抗アレルギー薬(飲み薬)
アレルギー炎症や気管支収縮を引き起こす物質の放出や産生を抑えることで、喘息症状を和らげます。
商品例:アイピーディ®、アレジオン®、インタール®、ザジテン®、ドメナン®、ベガ®、リザベン®など
これらの薬剤を適切に使い分け、継続して使用することは、喘息患者さんの日常生活の質を向上させるためにも不可欠です。
定期的な使用によって、喘息による生活の制限や発作に対する不安感を減らすことができます。
【参照文献】環境再生保全機構『 治療 ぜん息の薬』
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/knowledge/medicine.html
1-2.発作治療薬(リリーバー)
発作治療薬は、喘息発作が起きた際に即効性のある効果を発揮する薬剤です。
主に短時間作用性β2刺激薬が用いられ、気管支を拡張させる作用があります。これにより、呼吸困難や喘鳴などの症状を速やかに緩和することができます。
ただし、頻繁に使う必要がある際は、喘息がうまくコントロールできていないかもしれません。その場合は、早めに医師に相談し治療を見直すことを検討しましょう。
発作治療薬の使用例は次のようなものです。
1. 短時間作用性β2刺激薬
交感神経を刺激して気管支を拡張し、速やかに呼吸を楽にします。
商品例:サルタノール®、メプチンエアー®
2. テオフィリン薬(飲み薬)
気管支の緊張を和らげ、気管支を広げる効果があります。
商品例:ネオフィリン®
これらの発作治療薬は、一時的に症状を和らげるだけでなく、患者さんの毎日の生活をより楽にしてくれる効果もあります。
ただし、治療を発作治療薬だけに頼ると、気道の炎症が進み、症状が悪化する恐れがあります。日常的には、発作の予防や症状の管理のために長期管理薬を使用することが重要です。
ご自分で管理する場合に気をつけるポイントについては、次の章で詳しくご説明いたします。
【参照文献】環境再生保全機構『吸入器の特徴と注意点 吸入器の種類と吸入補助器具』
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/control/inhalers/feature01.html
2.吸入薬で咳が止まる?吸入薬は咳止めではありません

吸入薬を使うと、「咳が止まった」と感じる方もいらっしゃるでしょう。しかしながら、実は吸入薬は咳止めではありません。この点について違いを知っておくことはとても大切です。
吸入薬が咳を抑える効果があるように感じるのは、気道の炎症をおさえたり、気管支を広げたりする効果があるためです。
その結果として咳の症状が落ち着くことがありますが、これはあくまで喘息などの症状が改善されたことによるもので、咳を直接止めるものではありません。
また、風邪など急性の呼吸器症状に対して、一時的にネブライザーという器械で吸入を行うことがあります。この場合には、気道内の粘膜を潤したり痰を出しやすくしたりするために行われるので、咳止めとは異なる目的で使われています。
咳止めとの違いについては、以下の通りです。
咳止め
中枢神経系や末梢神経系での咳反射を抑制します。これによって一時的な咳の緩和には効果があります。
吸入薬
気道内に直接作用し、炎症や狭窄による咳反射を軽減します。このため根本的な改善につながります。
このような違いについて理解しておくことで、ご自身の症状への対処法についてより適切な判断ができるようになります。
ただし、自分自身で判断して服用した場合には、副作用やほかの健康問題につながる可能性があるので注意しましょう。
3.吸入器の種類

吸入薬を使用するための器具には主に次のような2種類があります。それぞれ特徴やメリットが違うため、自分やお子さまに合ったものを選べるよう医師と相談しましょう。
3-1.ドライパウダー吸入器(DPI)
ドライパウダー吸入器は粉末状の薬剤を吸入する器具です。この吸入器には以下のような特徴があります。
・吸気力で薬を吸入:患者さんが吸う力を使って薬を吸い込むタイプなので、薬が出るタイミングに合わせる必要がなく、自然に吸うだけで薬が気道に届きます。
・簡単な操作:ボタンを押したり調整する必要がないため、操作がシンプルで、忙しい日常生活の中でも手軽に使用できます。
・持ち運びやすい:小型で軽量なので、バッグやポケットにも入れやすく、外出先でも使いやすい設計です。
・吸気力が必要:吸う力が弱い方や小さなお子さまには、薬を十分に吸い込むのが難しい場合があります。お子さまや高齢者の方が使用する場合は、医師や薬剤師に相談すると良いでしょう。
湿気に弱い:粉末状の薬は湿気を吸うと固まりやすく、効果が落ちることもあるため、乾燥した場所に保管する工夫が必要です(例:湿気を避けた保管、乾燥剤の使用など)。
代表的なドライパウダー吸入器には、シムビコートやパルミコートなどがあります。それぞれに使い方のコツがあり、正しい方法で使用することが大切です。
また、最近は新しい製品も次々と登場しているので、ご自身やご家族の健康状態に合ったものを選ぶことが重要です。
3-2.定量噴霧式吸入器(MDI)
定量噴霧式吸入器は、薬を霧状にして吸い込むための器具です。このタイプには次のような特徴があります。
・ボンベ内の圧力で薬剤を噴霧:吸入器内のボンベに圧力がかかっており、ボタンを押すと薬が霧状になって出てきます。このため、比較的多くの患者さんに適した使いやすいタイプです。
・一定量の薬が放出される:1回押すごとに一定量の薬が噴霧されるため、用量を管理しやすく、決まった量を正確に吸入できます。
・吸うタイミングが重要:薬が噴霧されるタイミングと自分の吸うタイミングを合わせる必要があるため、最初は練習が必要です。しかし、慣れると効果的に薬を気道に届けられます。
・スペーサーとの併用が効果的:スペーサー(吸入補助器)を使うと、吸うタイミングを気にせずに薬をしっかりと吸い込めるため、とくにお子さまや慣れていない方にも安心です。
代表的な定量噴霧式吸入器には、フルティフォームやオルベスコなどがあります。それぞれに独自の使い方があるため、使用する前に確認することが大切です。
例えば、吸うタイミングやボタンを押す強さ、吸入後のうがいが必要かどうかなどが製品ごとに異なります。
最近は新しい技術を使った製品も増えてきているので、ご自分やお子さまに合ったものを見つけると良いでしょう。
ここまでご紹介してきたような吸入器は、前述のような吸入補助器(スペーサー)を使用することで、より効果的に薬剤を肺に届けることが可能です。以下は簡単な使用方法です。
1.吸入器をスペーサーに取り付けます。
2.スペーサーのマウスピースを口にくわえます。
3.吸入器を1回押して、薬剤をスペーサー内に噴霧します。
4.ゆっくりと約5秒かけて深く息を吸い込みます。
5.息を止めて10秒数えます。
6.ゆっくりと息を吐き出します。
スペーサーを使用することで、吸入のタイミングを合わせる必要がなくなり、より多くの薬剤が肺に到達します。とくに高齢者の方やお子さまにとって有用です。
3-3.吸入薬使用時の一般的な注意点
吸入薬は正しく使用することで、効果が発揮されます。ここからは使用する際の注意点を種類別にご説明します。
吸入薬の種類別の注意点
1. ドライパウダー吸入器(DPI)
使用前に容器を振る必要はありません。
強く深く吸い込むことが重要です。
湿気に弱いので、保管場所に注意が必要です。
2. 加圧噴霧式定量吸入器(pMDI)
使用前に容器をよく振ってください。
ゆっくりと深く吸い込むことが重要です。
吸入と噴霧のタイミングを合わせることが難しい場合は、スペーサーの使用を検討してください。
3. ソフトミスト吸入器
使用前に容器を振る必要はありません。
ゆっくりと深く吸い込むことが重要です。
初めて使用する際や長期間使用していない場合は、準備操作が必要です。
【参照文献】環境再生保全機構『正しい吸入方法を身につけよう』
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/control/inhalation.html
4.おわりに
ここまで見てきた通り、吸入薬は喘息をはじめとする呼吸器疾患の治療には欠かせない重要な役割があります。
一方で、繰り返しになりますが、「吸入薬は咳止めではない」という認識は重要です。
正しい知識で使用し、効果を理解することによって、ご自身やご家族の呼吸器疾患の症状を軽減し、より快適な日常生活を送ることができるでしょう。
咳止めといった誤った認識で、中途半端に吸入薬を使用することは、喘息の気道リモデリングの形成につながりますので、注意が必要です。
【気道リモデリングとは、気管支喘息などの慢性的な気道炎症によって気道の形態が変化し、気道壁が厚く硬くなる現象です。一度起こると治療しても完全に元に戻すことはできません。不可逆性で時間経過とともに悪化していくため、重症度が高く、治療に難渋することがあります。】
吸入器を処方された際には、医療機関や薬局で必ず使い方や注意点の指導を受けてください。
正しい使用方法を守ることで、より効果的な治療につながります。そして、定期的な診察も必ず受けましょう。きちんと使用できているか、吸入技術のチェックを受けることも必要です。
また、新しい製品や技術についての情報を積極的に収集することで、ご自分やご家族にとってより適切な治療選択肢を見つけられる可能性があります。
適切な治療と自己管理によって喘息とうまく付き合っていくことが可能です。ご自身だけではなく周囲とも協力しながら健康維持につながる生活習慣づくりに取り組みましょう。
喘息コントロールへの不安や疑問がある場合は、遠慮せずに主治医や呼吸器内科の医師へ相談してください。




