リンパ脈管筋腫症とはどんな病気?

リンパ脈管筋腫症(LAM)は、20~40代の女性にまれに発症する肺の病気です。
肺に「嚢胞(のうほう)」と呼ばれる袋状の空洞が多数できることで息苦しさを感じるようになります。
「最近息切れや咳が続いて、不安に思っていませんか?」こうした症状が長引く場合、この病気の可能性もあります。
適切な治療によって進行を抑えられる可能性がありますので、早めに専門医の診察を受けましょう。
1.リンパ脈管筋腫症とは
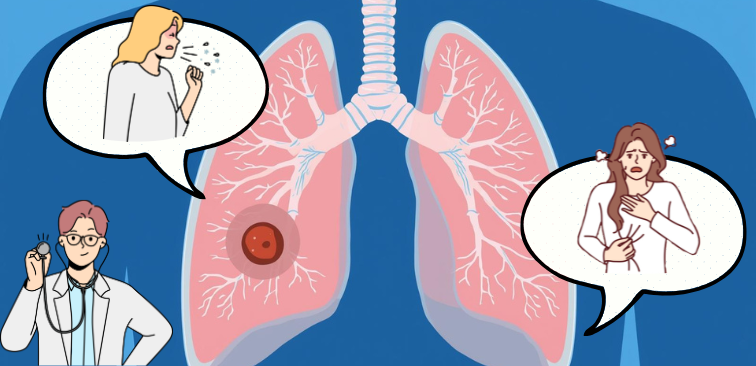
リンパ脈管筋腫症(LAM)は、女性ホルモンの影響を受けやすい20~40代の若い女性に多くみられる希少疾患です。
日本でも患者数はごく少なく、人口100万人あたり数人程度と推定されています。
LAMでは「LAM細胞」と呼ばれる平滑筋に似た異常な細胞が体内でゆっくり増殖し、主に肺やリンパ節、腎臓などに病変を作ります。その結果、肺の中には嚢胞(のうほう)と呼ばれる小さな空洞が多数形成され、肺が徐々に傷んで機能が低下していきます。
この病気は良性の腫瘍性疾患とも言われ、がんのように急速に悪化するものではありませんが、ゆっくりと進行して全身に影響を及ぼす特徴があります。
また、LAMは女性ホルモンとの関連が指摘されており、妊娠・出産や経口避妊薬の使用をきっかけとして症状が現れたり、病気の進行が早まる可能性があることが一部の研究で指摘されています。
【参考文献】“What Is LAM?” by National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI, NIH)
https://www.nhlbi.nih.gov/health/lam
1-1.原因について
リンパ脈管筋腫症(LAM)の明確な発症原因はまだ分かっていません。
しかし、多くの場合、体内の細胞の遺伝子に後天的(生まれた後に起こる)な異常が関与していると考えられています。
【参考文献】“Lymphangioleiomyomatosis” by StatPearls Publishing (NCBI Bookshelf)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534231/
1-2.2つのタイプについて
リンパ脈管筋腫症(LAM)には、大きく分けて2つのタイプがあります。
【結節性硬化症に関連するタイプ】
一つは「結節性硬化症」という別の病気に関連して起こるタイプです。
結節性硬化症は遺伝が関係する病気で、生まれつき細胞が異常に増えやすくなる特徴があります。
そのため、LAMを引き起こす異常な細胞が体の中で増えてしまいます。
【孤発性LAM(sporadic LAM)】
もう一つは、「孤発性LAM」と呼ばれるタイプです。
こちらは結節性硬化症のような他の病気と関係なく起こります。
孤発性LAMがLAM全体の約8割と多くを占めます。この場合も、細胞が後天的(生まれた後)に異常を起こして増えすぎてしまうことで病気が発症すると考えられています。
なお、孤発性LAMは生まれつきの遺伝が原因ではないため、家族や子どもに遺伝する心配はありません。
【参考情報】『リンパ脈管筋腫症』日本呼吸器学会
https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/i/i-06.html
2. リンパ脈管筋腫症の症状

リンパ脈管筋腫症(LAM)では、主に肺の症状が目立ちますが、肺以外のさまざまな臓器にも症状が現れることがあります。
ここでは具体的な症状を詳しくご説明します。
2-1.呼吸器に現れる主な症状
リンパ脈管筋腫症(LAM)の主な症状は肺の病変によって起こります。
初期には自覚症状がほとんどないこともありますが、病気が進行するにつれて運動時や階段昇降時の息切れ(労作時呼吸困難)が徐々に出現します。
日常的な動作で「息が切れる」感じが続く場合、運動不足と思って見過ごされがちですが、1年ほど慢性的に続く場合は注意が必要です。
また長引く咳(乾いた咳や痰を伴う咳)がみられることもあり、喘息に似たゼーゼーという呼吸音(喘鳴)が聞かれることもありますが、必ずしもすべての患者さんに見られるわけではありません。一部の患者さんでは血痰(痰に血が混じる)が出ることも報告されています。
◆『熱はないけど咳が止まらない時に考えられる疾患とは?』>>
【参考文献】“Lymphangioleiomyomatosis: a clinical review” by European Respiratory Society / Breathe
https://publications.ersnet.org/content/breathe/16/2/200007
2-2.気胸とその他の症状
リンパ脈管筋腫症(LAM)では肺の嚢胞が原因で自然気胸(肺が破れて空気が漏れる状態)を起こすことがあり、突然の胸の痛みや呼吸困難として現れます。
特に若い女性で原因不明の気胸を繰り返す場合、LAMが隠れている可能性があります。
気胸はLAMを発見するきっかけになりやすく、再発を繰り返す点も特徴です。
さらに、リンパ管から漏れた乳び(にゅうび)と呼ばれるリンパ液が胸にたまると乳び胸(水)、お腹にたまると乳び腹水となり、胸水による呼吸困難やお腹の張り(腹部膨満感)を引き起こすことがあります。
2-3.肺以外の臓器に起こる症状
腹部や骨盤のリンパ節に腫瘍ができるケース(リンパ脈管筋腫)や、腎臓に血管筋脂肪腫(AML)と呼ばれる良性の腫瘍ができるケースもあります。
腎臓の腫瘍は多くは小さく無症状ですが、まれに腹痛や腰背部痛、血尿を起こすことがあります。
このようにLAMは肺以外の臓器にも影響しうるため、多彩な症状が現れる可能性があります。
ただし症状の出方や進行速度には個人差が大きく、中には健康診断のレントゲンやCT検査で偶然に肺の嚢胞が見つかり、無症状のうちに診断される例もあります。
【参考情報】『リンパ脈管筋腫症(LAM)(指定難病89)』難病情報センター
https://www.nanbyou.or.jp/entry/173
【参考文献】“The Natural History of Lymphangioleiomyomatosis” by PMC / NCBI
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2883494/
3. リンパ脈管筋腫症の診断・検査

リンパ脈管筋腫症(LAM)は症状が特徴的ではないため、診断が難しい病気のひとつです。
そのため、専門医による詳しい検査が重要になります。ここでは診断のポイントや検査の方法について詳しくご説明します。
3-1.リンパ脈管筋腫症が疑われるのはどんなとき?
リンパ脈管筋腫症(LAM)は非常に稀な病気のため、診断には専門的な検査が必要です。
一般的に、喫煙歴のない若い女性で胸部CT検査にて両方の肺に多数の嚢胞が見られ、加えて自然気胸を繰り返したり徐々に息苦しさが悪化している場合は、LAMが強く疑われます。
CT画像上では数ミリから1センチ程度の大小さまざまな嚢胞が肺全体に分布しているのが特徴で、この所見は診断の重要な手がかりです。
また、腎臓に合併しやすい血管筋脂肪腫や乳び胸水・腹水の存在も診断の助けとなります。
さらに、結節性硬化症と既に診断されている方では、その女性患者の3~4割にLAMが見られるとの報告があるため、結節性硬化症患者さんを調べる過程でLAMが見つかることもあります。
◆『咳が止まらない場合に考えられる病気と検査・治療・予防について』>>
3-2.詳しい検査方法
リンパ脈管筋腫症(LAM)の確定診断のためには、画像検査に加えて病気を裏付ける検査が行われます。
他の肺疾患(例:喫煙が原因の肺気腫や、他の嚢胞性肺疾患)との区別をつけるために、医師は患者さんの症状や検査結果を総合的に評価します。
【 肺機能検査・血液検査】
必要に応じて肺機能検査(スパイロメトリーなど)で肺活量や1秒量を測定し、換気障害の程度を確認します。
また、血液検査では酸素や二酸化炭素の値を調べて呼吸不全の有無を確認します。
近年では、血液中のVEGF-D(血管内皮増殖因子D)という物質の値が高い場合にLAMである可能性が高いことが分かってきました。
このVEGF-D値はLAMの診断補助に有用で、一定以上の高値であれば侵襲的な手術なしでLAMと診断できるケースもあります(※ただしVEGF-D検査は特殊な検査であり、一部の施設で研究的に行われている段階です。すべての医療機関で受けられるわけではありません)。
【肺生検や細胞検査による診断】
最終的に確実な診断を行うには、肺生検(肺の組織の一部を採取する検査)や、胸水・腹水中の細胞検査によってLAM細胞の存在を病理学的に確認する方法があります。
臨床的な所見が典型的な場合には、生検なしでも総合的にLAMと診断されることがありますが、専門医による慎重な判断が必要です。
【参考情報】『リンパ脈管筋腫症(LAM)』慶應義塾大学病院 KOMPAS
https://kompas.hosp.keio.ac.jp/disease/000623/
4. リンパ脈管筋腫症の治療
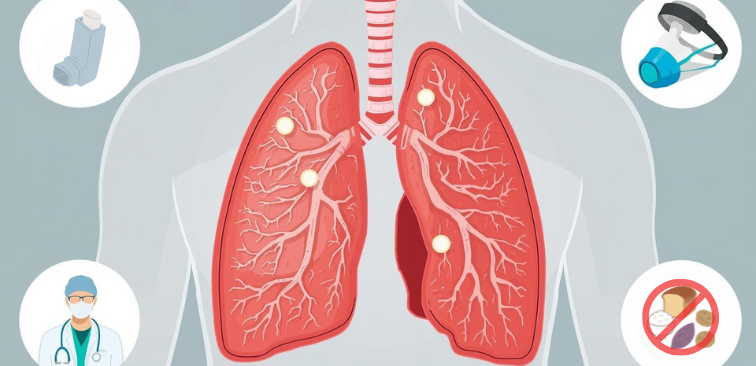
リンパ脈管筋腫症(LAM)には現在のところ完治させる治療法はありませんが、適切な治療により、症状の進行を遅らせ、症状和らげることが期待できます。
症状や肺機能の程度には個人差が大きく、ゆっくり進行する軽症例では経過観察(定期的な検査と通院)をしながら様子を見ることもあります。
4-1.呼吸器症状への対症療法
一方で、咳や喘鳴など閉塞性換気障害(息を吐き出しにくくなる状態)の所見がある場合には、気管支拡張薬(吸入薬など)を使用すると症状の改善に役立つことがあります。
呼吸が苦しく日常生活に支障が出る場合には、在宅で酸素を吸入する酸素療法を行い、体内の酸素不足を補います。
自然気胸を繰り返す患者さんには、再発予防のために外科的に肺の破れた部分を処置したり、胸膜を癒着させる治療(胸膜癒着術)を早めに検討することが推奨されています。
【酸素療法とは…チューブやマスクを使って酸素を吸入し、体の酸素不足を補う治療法です】
【参考文献】“LAM Management” by The LAM Foundation / provider guidelines
https://www.thelamfoundation.org/healthcare-providers/lam-management/
4-2. 乳び胸水や腹水、腎臓の腫瘍への対症療法
乳び胸水や乳び腹水が多量にたまる場合には、胸水・腹水のドレナージ(体内の余分な液を排出する処置)や食事の脂肪制限、必要に応じた外科的治療で症状緩和を図ります。
腎臓の血管筋脂肪腫に出血が生じ大量の出血リスクがある場合には、カテーテルによる血管塞栓術や外科的手術で止血・腫瘍摘出を行うこともあります。
4-3.薬物療法(シロリムス療法)
近年、リンパ脈管筋腫症(LAM)の病態解明が進み、新たな薬物療法が登場しました。
LAMでは細胞増殖の調節に関わるmTORというタンパク質の経路が常に活性化していることが分かっており、これを抑制する薬剤としてシロリムス(ラパマイシン)が開発されました。
国内外で行われた臨床試験の結果、シロリムスはLAM患者の肺機能低下の進行を抑える効果が確認され、多くの患者さんに問題なく投与されていますが、副作用のリスクもあるため専門医と相談しながら使用する必要があります。
日本でも2014年にシロリムスが承認され、現在は必要に応じて保険診療で処方可能です。
【シロリムスの効果】
シロリムス治療により、肺の機能低下を遅らせるだけでなく、合併している乳び胸水・腹水を減少させたり、腎血管筋脂肪腫を縮小させる効果も期待できます。
【シロリムス治療に伴う注意点】
ただし、シロリムスは免疫を抑える作用がある薬のため、感染症にかかりやすくなる、副作用でコレステロール値や血球数の変動が起こるなどの可能性があります。
このため、投与の際は専門医と相談しながら副作用に注意して治療を進める必要があります。なお、かつては女性ホルモン(エストロゲン)の影響を抑える目的でホルモン療法(GnRHアゴニストや黄体ホルモン製剤など)が試みられたこともありました。
しかし、現時点ではホルモン療法の有効性について統一した見解は得られておらず、十分なエビデンスがないため国際的なガイドラインでも推奨はされていません。
4-4.重症例への対応
リンパ脈管筋腫症(LAM)が進行して重症化すると、呼吸不全から肺移植(臓器移植)が検討される場合もあります。
日本でも非常にまれなケースですが肺移植を受けたLAM患者さんがいます。ただし、肺移植後にも、新たにLAM細胞による病変が再発したとの報告もあります。
移植が根本的な治癒策になるとは言い切れません。そのため、できるだけ移植に至らないよう、シロリムス療法や酸素療法などで病状をコントロールしながら、患者さんの生活の質(QOL)を維持していくことが大切です。
【参考情報】『リンパ脈管筋腫症(LAM)の診断と治療の進歩』日本内科学会雑誌
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/111/10/111_2107/_pdf
5. おわりに
リンパ脈管筋腫症(LAM)は若い女性に発症する珍しい病気ですが、適切な診断と治療により落ち着いた状態を保ちながら生活を続けることも可能です。
「最近、階段を上ると息切れがひどい」「原因不明の気胸を繰り返している」といった症状が2週間以上続く場合は、早めに呼吸器内科を受診して原因を調べてもらうことをおすすめします。
専門医の診察を受けて病名が分かれば、それまでの不安が軽減されますし、治療によって病気の進行を遅らせ症状を緩和することができます。
リンパ脈管筋腫症(LAM)は完治が難しい病気ではありますが、新しい薬剤(シロリムスなど)の登場により、症状の進行を緩やかにできる可能性があります。
患者さん一人ひとりの状況に合わせて最適な治療を続けることで、日常生活に支障の少ない状態を目指していきましょう。




