自治体から案内がきたら肺炎球菌ワクチンを接種しましょう
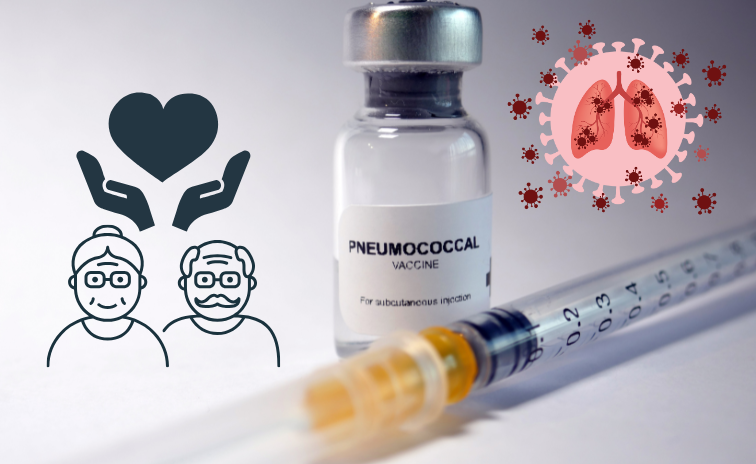
肺炎球菌は肺炎の原因として最も多い細菌であり、肺に感染する以外にも菌血症や敗血症など多くの感染症を引き起こす原因でもあります。しかし、肺炎球菌の感染はワクチンの接種で予防することが可能です。
高齢者の多くが肺炎で亡くなっている現状があります。
肺炎は予防が肝心。自治体から案内がきた方は肺炎球菌ワクチンを接種しましょう。
1.肺炎球菌とは?

肺炎球菌とは、その名の通り肺炎を引き起こす原因菌です。
肺炎の原因は様々ありますが、日常的にかかる肺炎の原因菌としては肺炎球菌が最も多いと言われています。
感染の経路は、小児の鼻やのどにあった肺炎球菌が咳やくしゃみで拡散され、それを人が吸い込んで広がっていきます。
肺炎球菌は体力のある方にとっては重篤な症状を引き起こすものではありませんが、免疫力の低下した状態の方や抵抗力が弱い方が感染すると、肺炎球菌感染症となります。
肺炎球菌による肺炎で亡くなる方の多くが65歳以上の方です。
加齢とともに体力が低下すると肺炎球菌に感染した際に症状を発症しやすくなりますので、大切なのは予防。毎日の手洗い、うがい、マスクの着用なども重要ですが、国が推奨しているワクチン接種も重症化を防ぐ手段として有効です。
【参考情報】Cleveland Clinic『Pneumococcal Disease』
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/24231-pneumococcal-disease
2.肺炎球菌ワクチン2種類について解説します

現在日本国内で接種可能な肺炎球菌ワクチンは2種類あります。
2-1.ニューモバックス®(23価肺炎球菌ワクチン)
ニューモバックス®は、90種類以上ある肺炎球菌の型のうち、23種類に効果のあるワクチンです。
ニューモバックス®ワクチンを摂取することで約4割程度の予防効果があるといわれ、現在行われている定期接種で用いられています。
接種対象者は65歳以上の方。また、60歳以上64歳未満で、心臓疾患、腎臓疾患、呼吸器疾患、HIV感染などによる免疫機能が低下している方なども対象となります。
接種は1回0.5mlを筋肉注射します。
接種前には、発熱していないこと、体調を崩していないことなどいくつかの確認事項とともに医師の診察を行います。また、基礎疾患のある方は、接種にあたり注意が必要となりますので、かかりつけの医師にご相談ください。
ニューモバックス®の接種は予防接種法に基づいた定期接種の対象となっています。
対象となる方は、65歳の方で、過去に成人用肺炎球菌ワクチンを摂取したことがない方です。
費用は医療機関により約8,000円〜10,000円程度ですが、多くの自治体では補助金の対象となっております。
ただしニューモバックス®の場合、免疫を維持するためには概ね5年毎に接種を受ける必要があります。
2回目以降の接種に関しては、現在のところ任意接種となっており、自治体の補助はありません。
2-2.プレベナー13®(13価肺炎球菌結合型ワクチン)
プレベナー13®は、肺炎球菌の型のうち、13種類に効果のあるワクチンです。
ニューモバックス®との違いは、長期間の免疫効果が期待できる点です。
免疫形成の機序が違うため、一度接種すれば生涯にわたり予防効果が期待できるといわれています。
ニューモバックス®と同じく、接種は1回0.5mlの筋肉注射です。
接種前には、発熱していないこと、体調を崩していないことなどいくつかの確認事項とともに医師の診察を行います。また、基礎疾患のある方は、接種にあたり注意が必要となりますので、かかりつけの医師にご相談ください。
※プレベナー13®は、プレベナー20®の発売に伴い2024年9月30日をもって販売終了しています。
2-3.プレベナー20®( 20価肺炎球菌結合型ワクチン )
プレベナー20®は、プレベナー13®が対応している13種に加え、計20種に対応する肺炎球菌ワクチンとして2024年10月より発売されました。
プレベナー13®と同様に長期間の免疫効果が期待できるワクチンで、1回の接種で生涯にわたり予防効果が期待できるといわれています。ただし、プレベナー20®は、成人の定期接種の対象となっていません。
接種回数は1回のみで、費用は医療機関により異なりますが8,000円〜12,000円程度です。
| ニューモバックス | プレベナー | |
|---|---|---|
| ワクチンの種類 | 多糖体ワクチン | 結合型ワクチン |
| 対応血清型 | 23種類 | 20種類 |
| 接種回数 | 5年毎に接種が必要 | 1回のみ |
| メリット | 広範囲をカバー | 免疫が長く続く・保菌を抑える |
| デメリット | 複数回の接種が必要 | 高額 |
【参考情報】『高齢者の肺炎球菌ワクチン』生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/pneumococcus-senior/index.html
3.接種をする際の注意点

肺炎球菌の予防接種を受ける際は、ワクチンの効果、接種回数、接種間隔、自己負担額などに注意が必要です。
一般的に費用負担が少ないニューモバックス®は初回のみ公費による補助が受けられますが、2回目からは自費となり5年毎の接種が推奨されています。
プレベナー20®やバクニュバンス®の場合は任意接種となりますが、一度の接種で生涯免疫が獲得できるといわれています。
ご自身の健康状態やライフスタイルなどを考慮し、医師と良く相談し検討することが望ましいでしょう。
肺炎球菌ワクチンの接種後は、接種部位の腫れや発赤、硬結、軽度の発熱など、ワクチン接種における一般的な副反応が起こる可能性があります。
既往症によっては接種にあたり注意が必要となる場合がありますので、かかりつけの医師によくご相談ください。
【硬結・・・一般に柔らかい組織が、炎症やうっ血、充血などで硬くなることをいう。組織損傷による出血、炎症、組織変性などによる急性期の硬結と、治癒後の硬結があり、後者を瘢痕という。】
4.インフルエンザの予防接種を検討しましょう

肺炎球菌ワクチンとともに、肺炎予防に有効なのがインフルエンザの予防接種です。
肺炎の原因の多くは肺炎球菌ですが、インフルエンザによっても肺炎を引き起こすことがあります。
インフルエンザは例年12月頃〜流行期を迎えるため、多くの医療機関では免疫効果が現れるまでの期間を考慮して10月頃から予防接種を開始します。しかし2024年は通常の流行期を前にインフルエンザの患者さんも見られており、より早い時期からの予防が重要となっています。
インフルエンザの感染経路は、くしゃみや咳による飛沫感染や接触感染のため、マスクの着用や手洗い・うがいなどをこまめに行うことで感染対策を行い、予防接種によって重症化を防ぐことができます。
インフルエンザワクチンも、定期接種として高齢者や小児を対象に補助金が出る自治体があります。大田区の場合ですと、65歳以上の方(または60歳以上で対象となる基礎疾患のある方)が10月1日〜来年1月31日までの間に対象医療機関で接種を受ける場合、自己負担額は無料です(2024年の場合)。
【参考情報】『インフルエンザワクチン(季節性)』厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/influenza/index.html
5.おわりに
肺炎は重症化すると命に関わる重大な疾患です。
特に免疫力が低下した高齢の方や持病をお持ちの方にとって、感染予防とともに重症化を防ぐ手段として、ワクチン接種が推奨されています。
肺炎球菌ワクチンも、インフルエンザワクチンも、接種すれば100%感染を予防できるわけではありません。しかし、感染した際の発症を予防することや、発症後の重症化や死亡を予防することに関しては一定の効果があるとされています。
自治体から接種に関する通知が届いた場合は、予防接種に関する説明をよく読み、ワクチンの有用性についてご確認ください。




